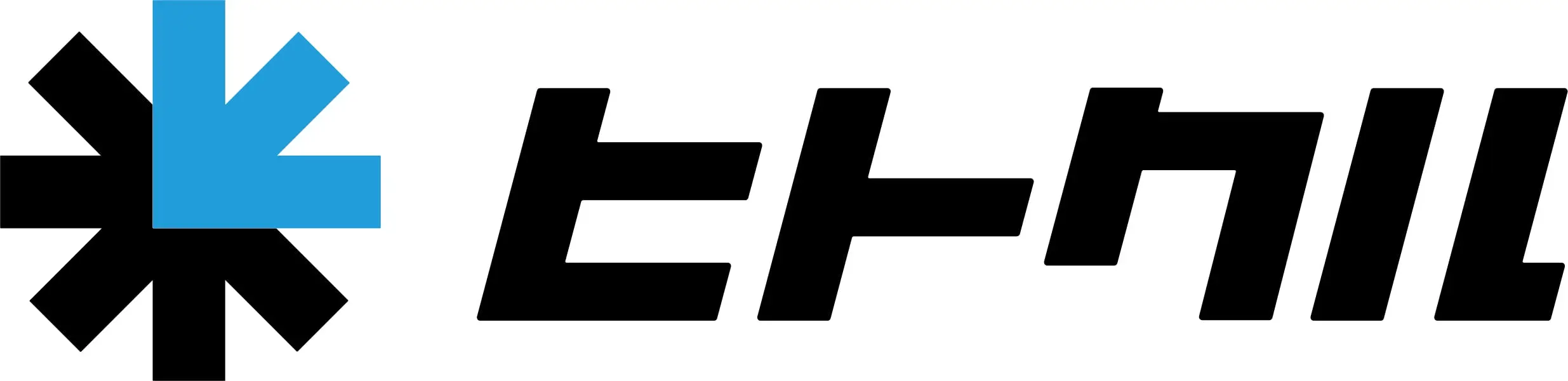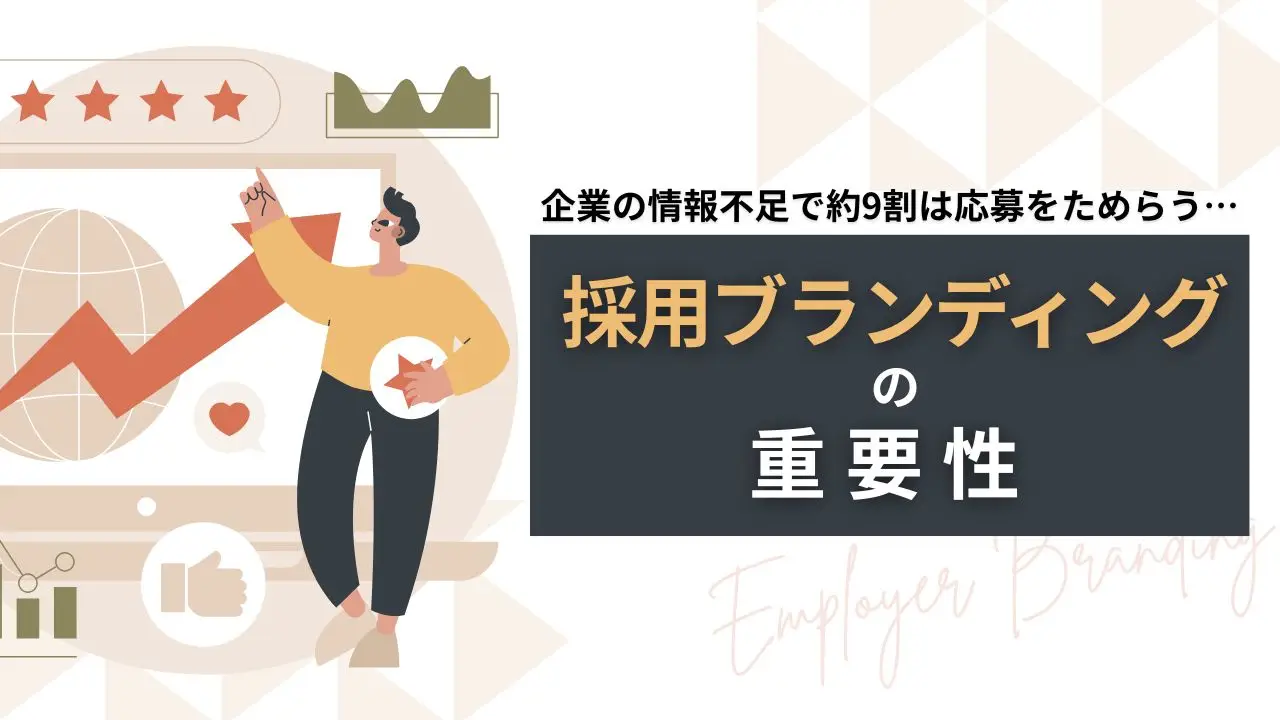
「部下の𠮟り方」令和へアップデートできていますか?
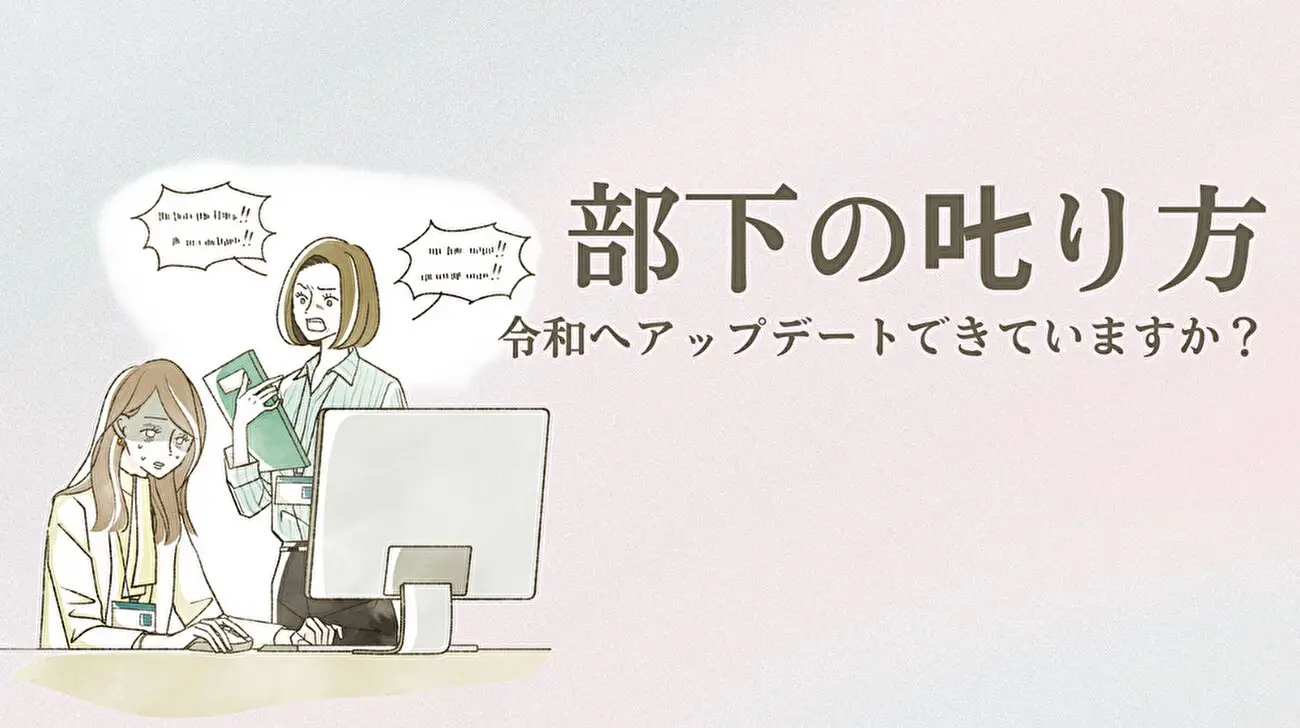
元CA、研修講師歴12年の「浪越あゆみ」と申します。
皆さんは、新入社員や若手社員の叱り方で、悩みを抱えていませんか?
ちょっとした言い方、伝え方でパワハラだと言われてしまう現在。
「部下を叱れなくて困っている」「部下に気になる部分があっても怒れない」「どこまで指導すれば良いのか考えてしまう」という上司が少なくありません。
注意をした結果、「部下の機嫌が悪くなり、職場の空気が悪くなってしまった」という声も、研修先で多く耳にします。
このような、考え方や価値観が違う令和入社の部下には、適した接し方があります。
この記事では、これから新入社員や若手の転職者を受け入れる方のために、令和の常識や効果的な叱り方を解説いたします。
Z世代の新常識とは

新入社員や若手社員との付き合い方で悩んだら、Z世代と呼ばれる彼らの新常識をまず理解するのがおすすめです。
Z世代は、怒らない育児、教育で育っているため「周りから怒られた経験がない」というケースが少なくありません。私もこれまでに、
「親にも、学校の先生にも怒られたことがないまま、社会人になった」
というZ世代を、多く目にしてきました。
このような環境で育つと、ちょっと大きな声を出しただけでも、「すごく厳しく怒られた」と捉えてしまいます。
高校で授業をする機会がときどきあるのですが、今の学校は、自分の学生時代では考えられないほど、先生方が生徒を叱りません。
一昔前は、居眠りしている生徒がいれば、ゲンコツされたり立たされたりするのが当たり前だったと思います。
しかし現在は、優しく注意をする程度で終わり。
ゲンコツや立たせるといった行動をしてしまったら、先生側が体罰や暴力だと取り上げられ、職を失う時代です。
このような、親にも先生にも叱られたことがない子どもが、いきなり第三者である会社の上司から怒鳴られたら……大きな衝撃として、記憶に残るのも無理がありません。
何が悪かったのか、理解したり反省したり前に、「キレられた!」というショックが先に立ち、「上司がパワハラ行為をしてくる!」と訴える可能性もあります。
Z世代と接するなら、怒られないで育った世代であること。
また現在のハラスメント教育を考えても、手をあげたり、強く叱ったりは時代に合っていないという点を覚えておきましょう。
パワハラを恐れて叱らない上司が増えている
会社を成長させるためには、雇用した若手社員を指導し、育てなければいけません。
その一方で、令和以降に入社した社員を前に、
「頭では分かっているけど、どうやって育てていけばいいのか?」
という悩みを抱えがちです。
近年「パワハラ」という言葉が広く知られるようになりました。
時代が変化する中、パワハラ認定を恐れる上司が増え、これまでのように叱る、怒鳴る、強く指導する、といった行為が難しくなっています。
ちょっとした発言でも、「パワハラ」と言われる今、話のきっかけを作ろうと、プライベートの話をちょっと振っただけなのに、今度は「セクハラ」「モラハラ」と言われてしまうケースもあります。
「彼氏はいるの?」
「一人暮らし?」
「今日の服、可愛いね」
「ランチでも行かない?」
「お茶入れてくれる?」
このような日常会話が、現在はタブーとされています。
「パワハラ・セクハラだと言われない言葉選びが分からない」と悩む上司も少なくありません。
「部下のためを思ってやさしく叱ったけれど、逆切れされて、よそよそしい態度になってしまった」という例もあり、若手社員と上司の付き合い方が難しくなっています。
「叱らないマネジメント」は本当に正解?
叱るのが怖い上司が増える現在ですが、「叱らないマネジメントで本当に良いのか?」という点についても考えておくべきです。
「怒る」と「叱る」は違う、というのは良く言われる話ですが、叱りすぎ、叱らなすぎも、部下の成長を止めてしまう可能性があります。
叱らないマネジメントを続けてしまうと、部下の問題が放置されてしまいます。
その結果、同じミスが何度も繰り返される未来になりかねません。
またZ世代は、「言われたことはとりあえずこなすが、それ以外はしない。自分で考えない※1」という現場の声もあり、マネジメントをしないままでは、指示待ち人間になってしまう恐れがあります。
※1 引用元:Z世代は「叱らない」の声も。半数以上がZ世代のマネジメントは難しいと回答。「ハラスメント扱いされる」「言われたことしかできない」など価値観の違いに悩みあり
このアンケート結果では、マネジメントの工夫として、「言われたことしかしないので、1から10どころか50くらいまで教える」という声も寄せられていました。
このように、相手がどこまでできているのかを把握して、しっかり教え込む、という行動ができると、成長に繋がる可能性があります。
叱られず、成長できない部下がいるチームや企業は、パフォーマンスにも影響が出がちです。
叱りすぎやパワハラになるような怒り方はNGですが、正しく叱る力、教えるスキルは必要といえます。
成長を求めるZ世代は叱られたい
Z世代の社員、令和入社の社員は叱るとすぐに辞めてしまう、逆切れする、パワハラだと訴えられる、そんなイメージが強いのですが、Job総研の「2023年上司と部下の意識調査」によると、全体の約20%の社員が「叱られたい・どちらかといえば叱られたい」と回答しています。
年代別にみてみると、「叱られたい・どちらかといえば叱られたい」と回答した20代は約25%となっていて、意外にも叱られたい割合がもっとも多い世代という結果になっています。
叱られたい理由(複数回答可)には、「自分の成長に繋がるから」という回答が約7割を占めていて、成長を求める人材は、年代を問わず叱られたい傾向があります。
その他にも、「自分をみてもらえている気になるから」「客観的な評価が欲しいから」という回答が約5割、「信頼を感じるから」という回答が約3割になっています。
「叱られるとモチベーションが上がる」も約22%という結果になりました。
この結果から、自己成長や上司との繋がり、信頼関係構築という面で「叱る」行為を求める層がいると分かります。
参考サイト:2023年 上司と部下の意識調査を実施しました/Job総研
令和入社の部下を上手に叱る方法
令和入社の部下は、叱られたくない訳ではありません。
自分のことを思って叱ってくれる上司、成長に繋がる指導であれば、受け止めたいと考える層が多い世代です。
この期待に応えるためには、まず上司が変わる必要があります。
「なぜ自分達が変わらないといけないのか?」
「変わらないといけないのはZ世代の子達だろう!!」
そう感じるかも知れません。
ですが、大人世代が経験してきた叱り方は、Z世代の子には受け入れられない方法です。
自分たちとはまったく違う、怒られない環境で育ったZ世代。
その常識を、古い考え方に変えるのは不可能だと認識して、令和流の叱り方をぜひ習得してください。
理解されない叱り方をずっと続けるより、ちゃんと伝わる𠮟り方・指導の仕方を選んだ方が、時間が無駄になりません。
受け入れられる言葉を選べると、上司側のストレスも減らせます。
「新入社員意識調査2025」から読み解く部下の価値観
部下を上手に叱るなら、令和の社員がどのような価値観を持っているのか、という点を知っておくと付き合いやすくなります。
株式会社リクルートマネジメントソリューションズが実施した、「新入社員意識調査2025」によると、働くうえで大切にしたいことのトップが「社会人としてのルール・マナーを身につけること(53.6%)」となり、2010に調査を開始してから、過去最高の数値になっています。
2位には「仕事に必要なスキルや知識を身につけること(43.7)」が入りました。社会人のルールやマナー、スキル、知識を教えるのは会社の役目のため、必要に応じて叱れる、指導できる上司の存在が必要だと分かります。
仕事・職場生活をするうえでの不安のトップは「仕事についていけるか(64.8%)」「自分が成長できるか(30.1%)」となっています。
成長を求める一方で、ついていけるかどうかを心配している新入社員が多く、部下のペースに応じた指導が重要視されそうです。
上司への期待には、「相手の意見や考え方に耳を傾けること(49.7%)」、働きたい職場のトップは「お互いに助けあう(69.4)」がトップになっています。
これらの結果から、仕事を通じて成長したいけれど、ついて行けるかどうか不安であり、自分の意見や考えに耳を傾けてほしい、助け合いたい、という若い世代の気持ちがみえてきます。
頭ごなしに叱るのではなく、部下の価値観を大切にしながら、最善の言葉を選ぶようにしてみてください。
参考サイト:「新入社員意識調査2025」の分析結果を発表/PR TIMES
Z世代に言ってはいけない叱り方7つ

Z世代に受け入れられる指導をする際、避けるべき逆効果な叱り方があります。
どのような言葉・態度がNGなのか、7つの例を紹介いたします。
1.人格や人権を否定する
容姿や性格、卒業校、家族構成などを否定する言葉は、若手社員の心を大きく傷つけます。
ちょっとからかったつもりだったのに、メンタルに不調を来たし、出社しなくなってしまった、という例もあります。
Z世代と接するならありのままを受け止め、冗談のつもりであっても、否定する言葉は使わないようにしましょう。
2.大声で怒鳴る
令和入社の社員に注意をする場合、必要以上に大声で怒鳴ったり、威圧感を与えたりする叱り方は厳禁です。
若手社員を萎縮させてしまうのはもちろん、大声で怒鳴る上司=感情のコントロールができない人、と思われる可能性があります。
できるだけ穏やかに、上下関係や声色で分からせるのではなく、同じチームでともに働く仲間として伝える姿勢を、大切にしてみてください。
3.他の社員がいる前で怒鳴る・叱る
上司や同僚など、同じ部署に人間が多くいる中で怒鳴ったり、叱ったりする行為は、Z世代のプライドを傷つけてしまいます。
注意や指導をしたい場合は、できるだけ他の人の目につかない場所を選びましょう。
このとき、二人きりになるような環境は、セクハラを疑われる恐れがあります。
上司と指導役と部下など、もう一人入れて話をする、同じフロアのパーテーションなどで区切られた場所を選ぶ、というのも良い方法です。
サービス業、接客業などの場合は、お客様の前で失敗を指摘しないようにしましょう。
人前での指導は、恥をかかされたという感情が芽生え、恨みや反発心が生まれる可能性があります。
飲食店などで、若手を厳しく叱った結果、SNSに怒鳴る様子が投稿されてしまった、というケースもあります。
良かれと思ってした指導が「こんなお店は行きたくない」というイメージに繋がるケースもあるため、叱る環境には特に注意してください。
4.以前の失敗を持ち出して叱る
若手社員だけの話ではありませんが、叱る際に以前の失敗を持ち出してしまうと、今なぜ怒られているのか、という点が曖昧になってしまいます。
できていない部分を注意していると、「そういえば前も……」「そういえばあの時も……」と昔のことを思い出しがちですが、相手に伝えるなら、今指導したい部分だけを短く叱る方法が効果的です。
過去の失敗やミスを持ち出して、くどくど叱る行為は控えましょう。
5.話を聞かず一方的に叱る
こちらもZ世代に限らずですが、部下が説明しようとしているのに、「言い訳はいらない」「まずは話を聞きなさい」といった言葉で話を止め、叱る行為は、相手の気持ちに寄り添わない行動です。
叱られる行動をした部下に非があるのはもちろんですが、なぜそうなってしまったのか、先に理由や原因に耳を傾けると、信頼関係を築けます。
「どうして、こんなことになってしまったの?」「何か理由があったなら聞かせほしい」そんな言葉を添えると、状況を把握しやすいですし、部下も「話を聞いてくれた!」という嬉しい気持ちになります。
その後の助言を素直に聞くきっかけにもなりますので、まずは相手の話へ寄り添ってみてください。
6.自分の若い頃と比べる
年配者がやりがちな叱り方の一つが、自分が若かった頃と比べて怒る、アドバイスする、という行動です。
これまでに「自分が若かった頃は、もっと努力していた」「先輩たちの指導はもっと怖かった」「お前たちは甘え過ぎだ」そんな言葉を言いながら、自分の厳しかった過去と比べて叱った経験はないでしょうか?
たしかに、今の40代以上はハラスメントが厳しい時代に、指導を受けてきた過去があります。
ですが、令和入社の社員は、怒りにまかせて叱るのはいけないことだと、学校教育などで教えられて、育っています。
Z世代へ大切なことを伝えるなら、過去との比較は止めて、「どうしたら問題を解決できるだろうか」と未来に向けた会話に変えていくと、受け入れられやすいでしょう。
7.同期や後輩と比べる
「同期や後輩と比較する」「できていない部分をバカにする」という叱り方も、やってはいけない行動です。
仕事を覚えるスピードや、得意不得意は一人ひとり違いますし、比べても問題解決には繋がりません。
できている人、スキルのある人と皮下気するのではなく、「未来の〇〇さんに期待しているよ。この問題を解決するにはどうすればいいか、一緒に考えていこう」といった流れで会話ができると、良い方向へ進みやすくなります。
Z世代の部下に思いが届く叱り方4つ

Z世代に言ってはいけない叱り方もあれば、思いが届く叱り方もあります。
若手社員のなかでも成長を求める層は特に、愛のある叱り、指導を期待しています。
次に、素直に受け止めて貰いやすい叱り方、部下に気持ちが伝わる叱り方をみてみましょう。
1.悪かった部分に気付いてもらう
部下を叱る行為は本来、二度と同じ問題が起きないように、何が悪かったのか気付いてもらうのが目的です。
感情的に怒鳴っても、次回からのミスがなくなったり、できていない部分に気付いたり、という未来には繋がりません。
その場の雰囲気、流れで怒るのは意味がないと、心得ておきましょう。
「ここが悪かったから、今度からこうしよう」という気持ちになってもらうために、どんな言葉が適しているのかを考える。
怒りの表情はおさえ、穏やかな雰囲気を意識する、といった点を大切にすると、気付きに繋がりやすくなります。
2.叱る場所とタイミングを考える
部下を叱るとき、タイミングの見極めがとても重要です。
思いついたときに言うのではなく、話を集中して聞ける場所を選んだり、業務の片手間ではなく、目を見て叱れるタイミングを見極めたりすると、相手に伝わりやすくなります。
部下が落ち着いて話が聞ける環境だけでなく、上司側の心が落ち着いている状態で叱る、というのも重要な部分です。
部下を叱る前に、自分の心を整えて、どの順番でどのように伝えるのか、シミュレーションしてから声をかけてみてください。
3.「あと良し言葉」を使う
「あと良し言葉」は、良くない内容を先に伝えたあとで、ポジティブな言葉、嬉しい情報を伝えるテクニックです。
部下を叱る場合は、指摘するべき部分に先に触れて、今度どうしていくのかを一緒に考えたあと、最後に「期待しているからね」「いつも丁寧に作業してくれて助かっているよ」といった、ねぎらいの言葉をかけてみてください。
「あと良し言葉」を意識すると、話をした後のムードが暗くならず、向上心が育ったり、モチベーションがアップしたり、という未来に繋がります。
「叱られたけれど悪い上司じゃない」といった捉え方になるため、叱った側への印象も良くなります。
その他にも「〇〇さんらしくないミスだけど何かあった?」という風に、「らしくない」という言葉を選ぶのも良い手段です。
あえて言わなくても、普段のあなたがちゃんとしているのを知っているよ、と伝えられます。
叱る際は、ただ事実を伝えるだけでなく、普段の頑張り、努力している姿を最後に言葉で添えてみてください。
4.解決策を自分で考えてもらう
ミスやトラブルが起きて、部下を叱らなければいけないとき、解決策を自分で考えるように促すと、上から目線で叱らずにすみます。
一方的に自分の考えを押しつけてしまうと、部下の成長を止めてしまう可能性があるため、注意しましょう。
気付きを成長の機会にできるように「まずは見守る」「対話の時間を増やす」という点を意識して、アドバイスを求められたときは快く答えてあげる、という姿勢を大切にしてください。
まとめ
今の40代・50代以上は、就職活動が厳しい時代に入社し、上司からは「背中を見て覚えろ」と言われ、必死にやってきました。
叱られる、怒鳴られるのは当たり前、という環境で指導されてきた世代が今になり、身につけてきた常識とは全く違った叱り方を求められるのは、正直大変だと思います。
ですが、時代は変わりました。
昭和の常識や指導を引きずっていては、若い社員と良い関係は築けません。
終身雇用制度が崩壊しつつある背景もあり、一方的に怒鳴ったり、叱ったりした結果、優秀な人材から「こんな古い考えの会社では、やっていけない」と見切りをつけられ、早期転職を選ぶケースが多くみられます。
若い社員と上手にやっていくなら、「令和の常識」を知り、「叱る目的」を考え、「相手に伝わる言葉」を選んでみてください。
上司のアップデートが、部下との関係を構築し、チームの団結力や会社の売上アップに繋がっていくはずです。
長崎県出身。長崎の大学を卒業後、客室乗務員へ。結婚を機に退職し、産後、客室乗務員で学んだことを活かし、研修講師に。客室乗務員の経験+マナーアドバイザーとして、四国を中心に社員研修・新人研修・接客指導・店舗接客改善アドバイスなどを行っております。またコミュニケーショントレーナーとして話し方セミナーや表現を学ぶセミナーも開講しています。
研修講師歴12年 これまでの受講者数約4万人
HP:https://lit.link/ayumilangyue