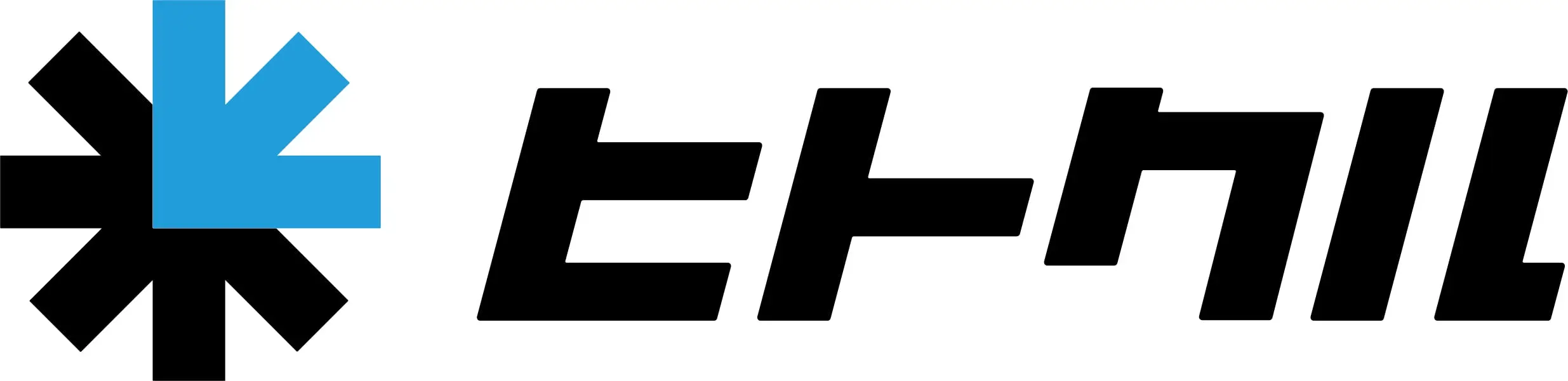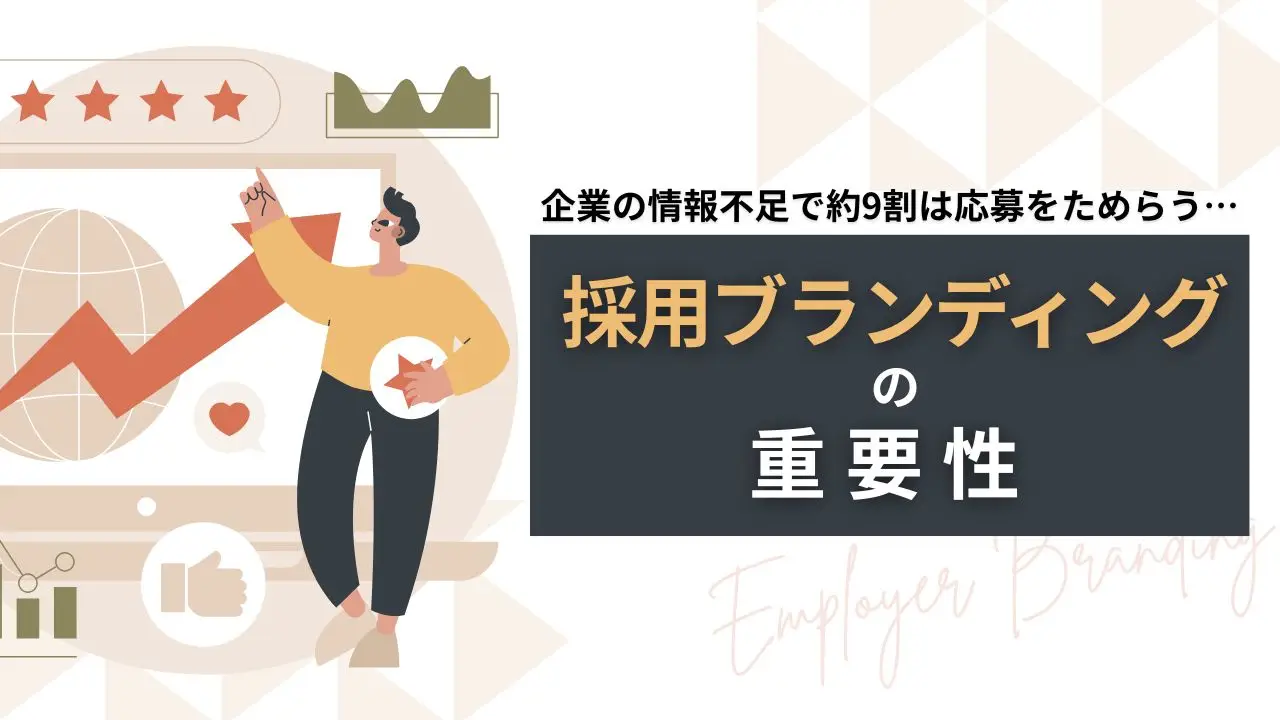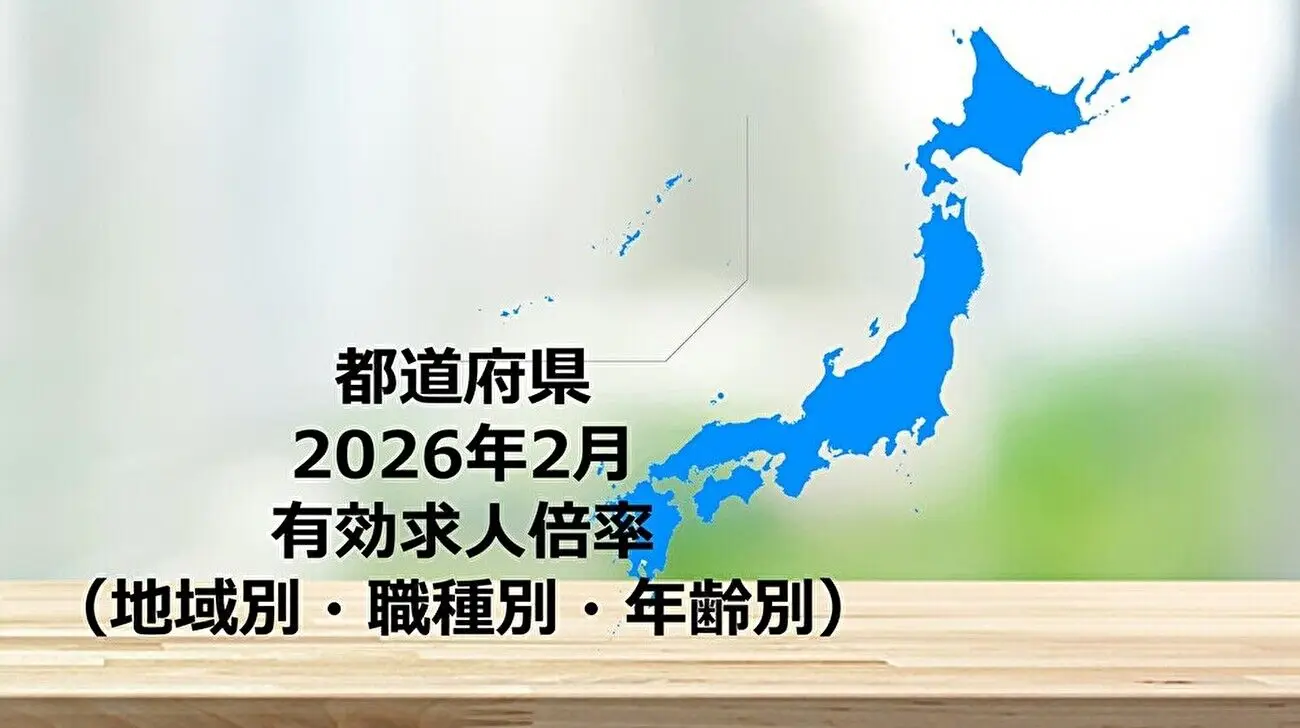
ミスマッチはなぜ起きる? 原因と未然に防ぐ予防法を解説!
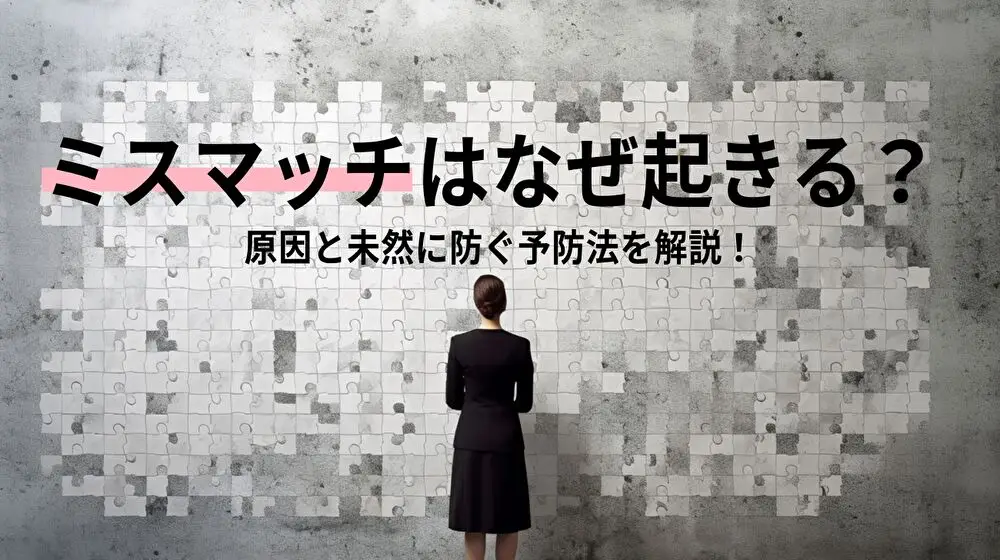
採用活動をしていると、採用したけれどすぐに退社してしまった、能力を発揮してもらえなかった、そんなミスマッチが起きるケースがあります。
ミスマッチが起きてしまうと、採用コストが増える、採用に関連する時間が無駄になる、といった負担が増えるため、予防策が必要です。
採用ミスマッチはなぜ起きてしまうのか、未然に防ぐ方法はあるのか。
今回は、ミスマッチが起きる原因と予防法について、詳しく解説いたします。
※社員の定着に必須?|リテンションの概要やメリット、代表的な取り組み事例を解説!
※ミスマッチを防ぐために、採用サイトで会社のリアルを伝えよう!
採用サイト制作なら、「ワガシャ de DOMO」がオススメ
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
採用におけるミスマッチとは
ミスマッチ(mismatch)は、英語で「不釣り合い」「不一致」という意味があります。採用の現場では、求職者と企業の間にずれやギャップが生じている状態を、ミスマッチと呼びます。
ミスマッチにはさまざまな種類があり、企業側の期待値が高すぎたり、応募者が企業や仕事についてよく確認していなかったりなど、多様な原因で発生します。
ミスマッチが起きてしまうと、内定辞退や早期退社につながる可能性が高くなるため、ずれやギャップが起きにくい採用活動が求められます。
ミスマッチによって早期退職してしまう社員は6割超にものぼる
マンパワーグループが2024年2月に行った人事担当者への調査によると、新卒採用において「特に問題なし」と答えたのは2割弱にとどまり、8割以上が何らかのミスマッチを経験していることが明らかになりました。
主な要因は「配属先の上司やメンバーとの相性不良」「仕事への意欲不足」「入社前の期待と実際の業務とのギャップ」が上位に挙がり、スキル不足や価値観の不一致も3割前後を占めました。
その結果、6割近くが早期退職に至り、配置転換や追加採用の必要性、人間関係の悪化、業績への影響など、企業側の負担増加につながっています。
参考:新卒採用におけるミスマッチは8割超!ミスマッチによる悪影響の1位は採用した社員の早期退職/マンパワーグループ
アンマッチとの違いを解説
ミスマッチと似た言葉に、アンマッチ(unmatch)があります。
アンマッチは、採用企業が求める学歴や経歴、スキルを持った人材が集まらず、採用できなかったケースを指します。
希望する人材を採用できなかった場合はアンマッチ、採用できたけれど企業と応募者側の考えや希望が合わない場合はミスマッチとなりますが、アンマッチも含めミスマッチと呼ぶ例もみられます。
※ミスマッチを防ぐために、採用サイトで会社のリアルを伝えよう!
採用サイト制作なら、「ワガシャ de DOMO」がオススメ
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
採用担当者を悩ませる5つのミスマッチ
ミスマッチには、どのような種類があるのでしょうか?
採用者の離職を防ぐために、よくある5つのミスマッチ事例をみてみましょう。
採用条件の相違によるミスマッチ
「基本給が求人内容と違っていた」
「残業が思っていたより多かった」
など、企業が出した採用条件が、求職者にきちんと伝わっていないパターンです。
求人広告の情報に不足がないか、採用条件を伝えるための説明会や相談の場は足りているか、といった部分に注意すると、採用条件でのミスマッチを防げます。
社風や文化によるミスマッチ
「年功序列で若い人材が意見を言いにくい」
「家にいたいのに、定期的な飲み会がある」
など、企業の社風や文化と、応募者の考え方が合わないパターンです。
考え方を変えるのは難しいこともあり、自分に合わない会社だと、退社を選ばれてしまうでしょう。
候補者の考えや希望と自社の社風、文化がマッチしているかどうか、先輩社員との交流会や社内見学、インターンシップ制度の導入などで、確かめる機会を設けておくと、ミスマッチを減らせます。
※インターンシップ採用とは?種類や特徴、導入手順について徹底解説
仕事内容への不満によるミスマッチ
「接客がしたかったのに裏方を任された」
「事務作業を希望していたけれど、現場に配置された」
など、配属の際に希望する業種、部署に就けなかったパターンです。
やりたいことができない環境を前に、離職という選択肢を選ぶケースが少なくありません。
人材採用の段階で、どのような働き方を望んでいるのか、業務内容の希望はあるのか、という点を確認して、仕事内容への不満が起きないようにしましょう。
実力不足によるミスマッチ
「知らない言語でのプログラミングを指示された」
「経験が無いのに、チームリーダーに任命された」
など、採用活動時における、応募者の学歴、経歴、スキルなどの確認が足りなかったパターンです。
企業が求めているスキル、能力に満たない社員を雇用してしまうと、従業員にも採用側にもストレスとなってしまいます。
書類選考や面接、適性検査などで候補者の能力を事前に確かめて、実力不足という結末を招かないようにしましょう。
コミュニケーション面でのミスマッチ
「一緒に働く先輩社員と気が合わない」
「上司が無口な性格で、日々の業務を進めづらい」
など、社員同士や上司との相性が合わないパターンです。
交流会や面接を通じて、候補者の性格、人柄をチェックの上、最適な部署へ配属しましょう。
人間関係の悩みを相談できる相手を作っておくと、離職を未然に防げます。
なんでも話せる風通しの良い環境、必要に応じて速やかに配置転換できる仕組みを整えて、コミュニケーション面での不満を減らしましょう。
※ミスマッチを防ぐために、採用サイトで会社のリアルを伝えよう!
採用サイト制作なら、「ワガシャ de DOMO」がオススメ
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
ミスマッチがもたらす3つのデメリット
ミスマッチが起きやすい状態が続くと、企業にとって大きなデメリットとなります。
最後に、ミスマッチがもたらすマイナス面を確認しておきましょう。
デメリット1:売上や品質に影響が出る
企業とのずれやギャップを感じている従業員がいると、モチベーションが低下してしまいます。
やる気が起きない社員の存在は、チーム内のコニュニケーションにも悪影響を及ぼすでしょう。
サービスやものづくりの品質低下にも繋がりやすく、顧客からの信頼を損なったり、売上が落ちたり、という恐れがある点もデメリットです。
デメリット2:社員がすぐに辞めてしまう
ミスマッチが起きやすい職場は、早期離職が起きがちです。
従業員が減ってしまうと、既存社員の負担が増えたり、不満を抱えたり、という影響があるため、ミスマッチ低減の試みが欠かせません。
場合によっては、これまで頼りにしていた上司や先輩社員が退社を選ぶ場合もあります。
採用人材の入社後フォローだけでなく、既存社員へのフォローも忘れないようにしましょう。
デメリット3:採用コスト・育成コストが無駄になる
時間や費用をかけて採用した人材が辞めてしまうと、企業にとって大きな痛手になります。
新入社員教育、指導を進めていた場合、より負担コストが大きくなるでしょう。
人材の退職によるフォローのために、アルバイトや派遣社員を雇用する、既存社員が残業して業務対応する、といった余計なコストが発生する場合もあります。
採用コスト、育成コストを無駄にしないためにも、ミスマッチ低減の施策を取り入れましょう。
※参考:エンジニアの退職理由で多いものは?採用後のミスマッチを防ぐ方法を紹介 | SES業務管理の統合ツール Fairgrit®公式サイト
ミスマッチが起きてしまう4つの理由
雇用ミスマッチが起きやすいという場合、採用活動や入社後サポートに問題があるかも知れません。なぜミスマッチにつながってしまうのか、よくある4つの理由をみてみましょう。
企業のマイナス面を伝えていない
採用活動を円滑に進めるために、つい自社の良い部分ばかりをアピールしているケースです。
企業の魅力を感じて貰えないと、応募や採用につながりません。だからといって、マイナス面を隠してしまうと、「思っていた働き方ではなかった」「想像していた待遇と違った」そんな理由で離職を選ばれてしまいます。
「○時間程度の残業があります」
「土日祝日に出勤する場合があります」
「近隣エリアへの出張や転勤があります」
など、自社の魅力だけでなく、応募者にとってマイナスとなる面もしっかり伝えると、デメリットを理解した上で入社してもらえるため、早期離職の可能性を減らせます。
採用段階と入社後の話にずれが生じている
採用の段階では、○○の職種だと聞いていたのに、いざ入社したらまったく違う部署に配属された、聞いていた待遇で迎えて貰えなかった……このようなずれがあると、安心して勤務できません。
企業への信頼が薄れたり、やりがいを失ったり、という結果になってしまうため、情報は正しく共有しましょう。
業務内容や配属先、待遇について、変更がある場合は早めに連絡の上、相談できる窓口を設けるなど、安心して働けるサポート体制を用意しましょう。
求職者の考え方・希望を把握できていない
書類選考や面接、内定式や交流会など、応募者の考えを知る機会がありますが、本音の部分まで把握するのは簡単ではありません。
ミスマッチを低減するために、対話する機会をできるだけ持ち、コミュニケーション不足に陥らないようにしましょう。
昇級や昇格についてなど、応募者からは聞きづらい部分を、企業側から先に伝えるのも良い方法です。求職者が自分の意見を気軽に話せるように、カジュアル面談を導入する、交流会を複数回開催する、といった施策も検討しながら、人材への理解を深めましょう。
※内定者懇親会は必要? フォローの重要性や進め方・注意点を解説
入社後フォロー・サポートが実施されていない
入社後にミスマッチの恐れがある場合も、人材へのフォローやサポートができていれば、希望と違う職種だけど頑張ってみよう、想像と違う部分もあったけれどやってみよう、そんな前向きな気持ちを引き出せます。
採用担当者からこまめに声をかけたり、人間関係やコミュニケーションの様子を観察したりして、採用人材が悩んだり困ったりしていないか、チェックしましょう。
社員の不安や不満が募る前に、手厚いフォロー・サポートを用意してください。
今すぐ取り入れたい! ミスマッチ予防法5選
今後のミスマッチを防ぐために、企業として取り入れるべき方法がいくつかあります。
今すぐ検討できる、5つの予防法をみてみましょう。
1.採用条件のミスマッチがないか確認する
求職者に提示している仕事内容、給与、待遇、残業時間、転勤の有無といった情報に間違いがないか、正しく伝えられているか、採用をはじめる前にチェックしておきましょう。
現在の情報ではデメリットが伝わりづらい、良い部分ばかりの内容になっている、という場合は、見直しが必要です。
採用担当者だけでは、気付きにくい部分もあります。新入社員を対象に分かりにくい部分やイメージと違う点がなかったか確認する、第三者目線でチェックして貰う、という方法もおすすめです。
2.会社の雰囲気が伝わる時間を持つ
コミュニケーション関係、企業理念との相違などでのミスマッチを防ぐために、事前に会社の雰囲気、思いを伝える場が必要です。企業の良い部分だけでなく、今後の課題や現在抱えている問題なども交えながら、事実が伝わるようにしましょう。
企業の雰囲気を知ってもらうなら、実際に足を運んで貰うのが一番です。難しい場合は、先輩社員の声を集めて共有する、社内案内する動画を見てもらう、といった方法で、積極的に中身を知ってもらいましょう。
3.リファラル採用を導入する
リファラル採用は、自社で働いている社員からの推薦・紹介で人材を募る制度です。
企業の雰囲気や働くメリットを知っている人材からのアプローチのため、入社後のミスマッチを低減できます。
従来の縁故採用とは違い、リファラル採用は紹介であっても書類選考や面接を経て、採用不採用を判断します。誰でも採用する制度ではないことから、よりミスマッチ減に繋がります。
4.リファレンスチェックを実施する
求職者の実力不足を未然に防ぐなら、どのような実績・スキルを持っているのか、自己PRの内容に間違いはないのか、といった点を調査する、リファレンスチェックを実施してみましょう。
前職調査と似ていますが、経歴だけでなく、企業でどのような活躍をしていたのか、コミュニケーションに問題は無かったか、といったリアルな部分をチェックできるのが特徴です。
応募者、応募者の上司に許可を得た上で、人柄や一緒に働いてみて感じたことなどを聞き、ミスマッチ防止に生かしましょう。
5.入社後のフォロー・サポート体制を見直す
入社後のフォロー・サポート体制が行き届いているか、採用前に確かめておきましょう。
不足している場合は、メンター制度を導入する、定期的に面談の時間を設ける、食事会や社内イベントなど交流の場を持つ、といった方法で、気持ちよく働ける環境を整えてみてください。
キャリアプランを作成する、将来のビジョンを共有する、という手法もあります。未来を考えることで、ポジティブな気持ちで仕事へ取り組めるようになる、先を見据えて長く働いて貰える、という点がメリットです。
社員のやりがいが見つかる企業、夢をサポートできる企業体制で、ミスマッチを減らしましょう。
※ミスマッチを防ぐために、採用サイトで会社のリアルを伝えよう!
採用サイト制作なら、「ワガシャ de DOMO」がオススメ
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
ミスマッチが起きてしまったらどうしたらいい?対処法3ステップ
採用後にミスマッチが発生してしまった場合、適切な対処が必要です。
まずは問題を放置せず、早期発見・早期対応を心がけましょう。
ミスマッチを解消するには、「ヒアリング」「解決策の検討」「再発防止」という3つのステップが効果的です。
これらのプロセスを丁寧に踏むことで、退職という最悪の結果を回避できる可能性が高まります。
社員との信頼関係を築きながら、組織と個人の双方にとって最適な解決策を見つけていくことが重要です。
以下では、それぞれのステップについて具体的な進め方を解説していきます。
ステップ1:まずはヒアリングする
ミスマッチが発生した場合、まず行うべきは当事者からの丁寧なヒアリングです。
「なんとなく合わない」という漠然とした感覚を放置せず、具体的に「どの業務に違和感があるのか」「入社前に描いていた仕事内容とどう違うのか」「どのような環境であれば力を発揮できるのか」といった点を詳細に聞き取りましょう。
この際、相手を責めたり、指導したりするようなトーンではなく、協力してより良い状態を目指す前向きな対話を心がけることが重要です。
特に入社3ヶ月以内の社員からは、外部者の視点で気づいた組織の課題が聞けるチャンスでもあります。
ヒアリングは、本人の話を傾聴し、本質的な原因を究明するのが目的です。
アドバイスなどは控えめにし、本人の話を引き出すことに注力しましょう。
このプロセスを通じて得られた情報が、次のステップでの解決策立案の土台となるのです。
ステップ2:解決策を話し合う
ヒアリングで把握した課題を基に、次は具体的な解決策を見つけるフェーズに移ります。
上司、人事担当者、そして当事者本人を交えた話し合いの場を設けましょう。
もちろん本人の希望通りに行かないことはありますが、ここでは一方的な押し付けではなく、全員が納得できる妥協点を探ることが重要です。
業務内容の見直し、配属部署の変更、追加研修の実施、メンター制度の導入など、状況に応じた対応策を検討します。
特に「できること」と「できないこと」を明確にし、実現可能な範囲で調整することがポイントです。
また、勤務時間や働き方の柔軟化、コミュニケーション方法の改善なども有効な解決策となります。
話し合いの結果は必ず文書化し、進捗を定期的に確認する仕組みも作りましょう。
双方が歩み寄ることで、思わぬ良い結果に繋がることも少なくありません。
ステップ3:原因を分析し再発を防止する
ミスマッチが発生した後は、その原因を徹底的に分析し、同じ問題が繰り返されないよう対策を講じることが重要です。
ステップ1での当事者へのヒアリング結果や上司・同僚からの情報をもとに、ミスマッチが生じた真の原因を特定します。
採用面接での説明不足だったのか、求人票と実際の業務内容に乖離があったのか、あるいは入社後のフォロー体制に問題があったのかを明確にしましょう。
次に、採用プロセス全体を見直し、どの段階で情報の乖離が生じたのかを特定します。
求人票の記載内容、面接での説明事項、入社前の情報提供資料など、すべての接点を検証してください。
そして、明らかになった問題点に基づいて、採用基準の見直し、面接官トレーニングの実施、入社後フォロー体制の強化など、具体的な改善策を実行に移します。
定期的に効果を測定し、必要に応じて対策を調整することで、採用ミスマッチの再発防止に繋げることができます。
やってはいけない!ミスマッチの間違った対処法3つ
ミスマッチが発生した際、焦りから取ってしまいがちな間違った対応があります。
これらの対処法は問題を悪化させるだけでなく、貴重な人材を失う原因にもなりかねません。
これらの対応は短期的には楽に見えても、長期的には組織に大きなダメージを与えることを理解しておく必要があります。
ここからはミスマッチに対する典型的な間違った対処法を3つご紹介します。
取り合わない
ミスマッチを感じている社員の声に耳を傾けないことは、避けるべき対応です。
「合わない」「違和感がある」という申し出を無視したり、「慣れれば大丈夫」と軽視したりすることで、問題は解決しません。むしろ逆効果です。
声を上げた社員は自分の意見が尊重されていないと感じ、孤立感を深めていきます。
その結果、不満やストレスが日々蓄積され、モチベーションの低下、パフォーマンスの悪化を招き、最終的には離職という最悪の結果に繋がりかねません。
ミスマッチの兆候が見られたら、まずは真摯に向き合い、対話の機会を設けることが重要です。
頭ごなしに叱責する
ミスマッチを感じている社員に対して「やる気がない」「努力が足りない」と頭ごなしに叱責することは、問題解決どころか状況を悪化させてしまいます。
このような対応は社員の自己肯定感を著しく低下させ、職場への不信感をさらに強めてしまいます。
社員が職場への不信感を持つと本音で話さなくなってしまい、コミュニケーションが悪化します。
このような対応はミスマッチを「社員個人の資質の問題」だと誤解していることで発生しやすいです。
ミスマッチは「プロセスや仕組みの問題」であり、個人の問題ではないことをまず認識しましょう。
ごまかしや精神論で乗り切ろうとする
ミスマッチが発生した際に「3年は頑張ろう」「真摯に頑張っていればいつか花開く」といった精神論でごまかそうとする対応は、問題の根本解決にはなりません。
このような曖昧なフォローは、一時的に状況を取り繕うだけで、実際には社員の不満や違和感を放置することになります。
また「来年になれば異動願いが出せる」「今のプロジェクトが終われば希望の職場に行ける」といった確証の無い見返りを約束して先送りしてしまうのも非常にリスクの高い行為です。
そのときになって約束が果たされなかった場合には、社員の不信感はさらに高まってしまいます。
結果的に、小さな問題が大きく膨れ上がり、突然の退職という形で表面化することになります。
ミスマッチは具体的な原因があるからこそ生じる問題です。
精神論ではなく、実際の業務内容の調整や採用・教育プロセスの改革など、具体的な解決策を提示することが重要です。
ミスマッチ解消の成功事例3つ
採用ミスマッチを解消した企業の成功事例を見ていきましょう。
リファラル採用でミスマッチ解消(株式会社ディンプル)
株式会社ディンプルでは、リファラル採用を積極的に活用してミスマッチ解消に成功しています。
同社は、ホスピタリティ業界に特化した人材紹介・派遣サービスを提供していますが、以前は入社後の早期離職が課題でした。
そこで導入したのが、従来の募集チャネルに加え社員経由の「お友達紹介キャンペーン」です。
リファラル採用を本格導入した結果、紹介経由で入社した人材の離職率が低い傾向が確認されました。
紹介で来社・登録した応募者の採用転換率も90%近くに達し(通常は25~30%程度)、採用コストも削減できたといいます。
紹介者である社員との信頼関係や事前の生の情報共有により、企業文化や仕事内容への理解度が高い人材を採用できたことが要因と考えられます。
参考:リファラル採用で”離職率、派遣登録率、採用コスト”を改善した秘訣とは/Refcome
新人研修期間の延長で定着率大幅アップ(株式会社アイネット)
株式会社アイネットでは、新入社員の早期離職問題に直面していましたが、研修期間の大幅な見直しによって劇的な改善を実現しました。
従来2ヶ月だった研修期間を6ヶ月に延長し、段階的なスキル習得プログラムを導入したのです。
この延長期間中、新人社員は実務に触れながらも過度なプレッシャーを感じることなく、基礎スキルを確実に身につけられるようになりました。
この取り組みにより、技術的な質問だけでなく、職場環境や社風に関する不安も気軽に相談できる環境が整いました。
結果として、新卒3年以内の離職率は6〜10%程度に減少。
メンタルヘルスを理由とした社員の休職の低減にも繋がり、健康経営にも繋がったと語っています。
参考:若者が定着する職場づくり取り組み事例集/公益財団法人日本生産性本部
マンツーマンのメンター制度で離職率大幅減(カネテツデリカフーズ株式会社)
カネテツデリカフーズ株式会社では、以前「仕事は見て覚えろ」という古い体質が根付いており、新入社員へのノウハウ共有やコミュニケーションが不足していました。
この状況を改善するため、同社は「指導員制度」を導入。
新人一人に対して先輩社員一人が専属の指導員となり、業務指導だけでなく精神面のサポートも行う体制を構築しました。
特に注目すべきは、月に一度の指導計画書の策定と明確な目標設定・フィードバックの時間を設けたことです。
この取り組みにより、新人が抱える不安や疑問をタイムリーに解消できるようになりました。
さらに、メンター側も指導スキルを磨く機会となり、組織全体のコミュニケーション文化が活性化。
結果として、かつて50%を超えていた入社3年以内の離職率が10%にまで劇的に低下し、人材定着と技術継承の好循環が生まれています。
参考:若者が定着する職場づくり取り組み事例集/公益財団法人日本生産性本部
まとめ
ミスマッチの少ない採用活動を実践できると、企業の成長を促せる、風通しの良い職場を整えられる、といったメリットが待っています。
できるミスマッチ予防法から取り入れて、自社に合った人材を獲得してください。
ミスマッチが少ない企業になれば、採用人材の経験、スキルが業務に生かされるため、既存社員からの自社評価アップにもつながります。
企業のありのままを伝える、応募者の考え方や希望を聞く機会を持つなど、ずれやギャップが生じにくい方法を選んで、求職者が活躍できる企業を目指しましょう。
※ミスマッチを防ぐために、採用サイトで会社のリアルを伝えよう!
採用サイト制作なら、「ワガシャ de DOMO」がオススメ
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。
「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。
アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/