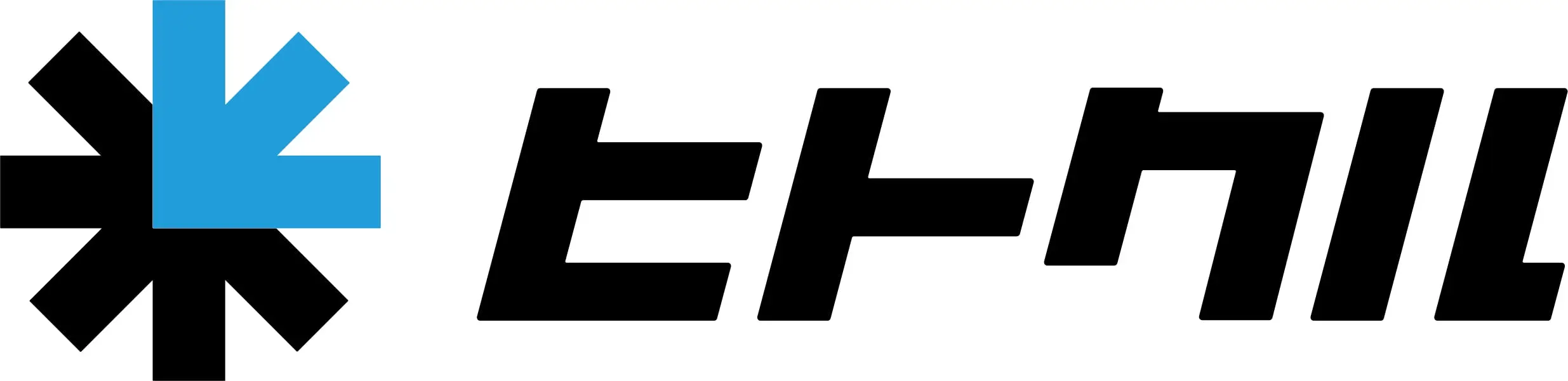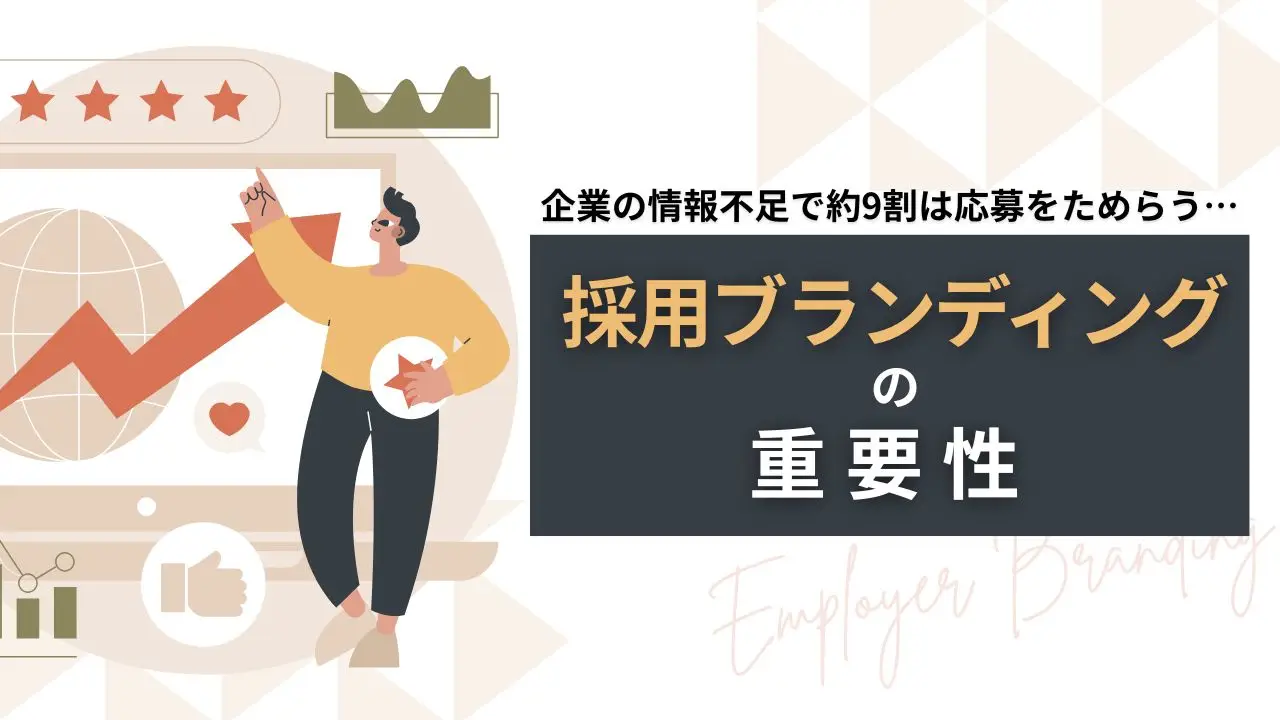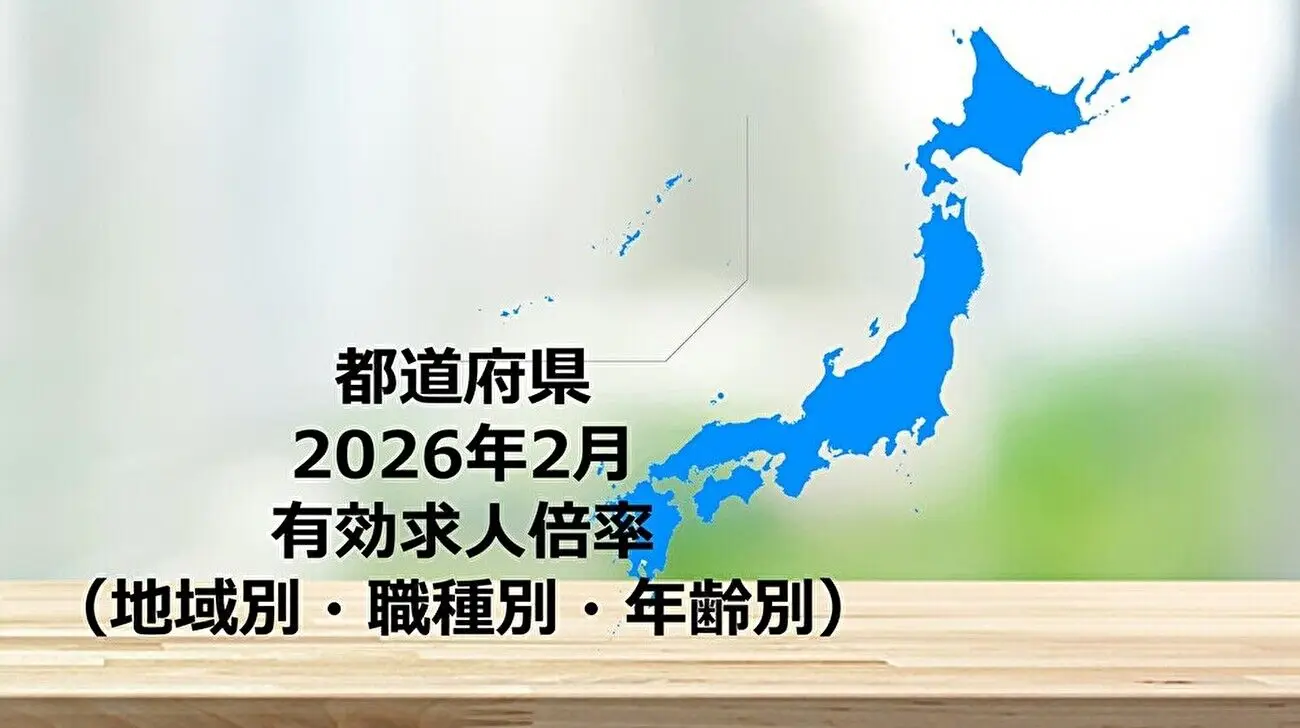
労働力不足改善に必須|嘱託社員の定義やメリット・デメリット、制度導入の秘訣とは
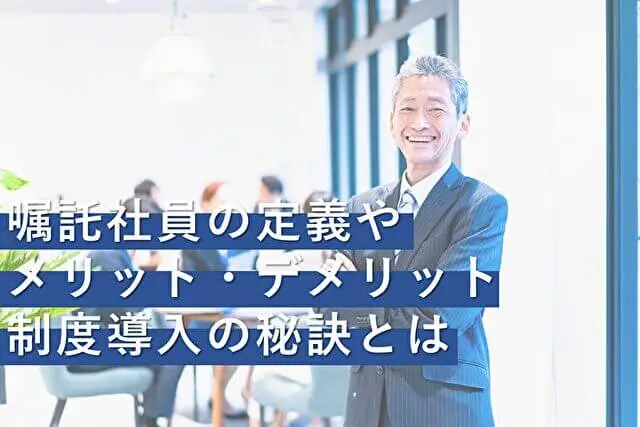
近年、少子高齢化の影響による労働力不足に伴い、嘱託制度を導入する企業が増えています。
新たな労働力を確保する施策として取り組まれている嘱託ですが、業務委託や契約社員との違いはどのような点にあるのでしょうか。
そこで、本記事では嘱託の定義や業務委託・契約社員との違い、嘱託社員を雇用するメリットやデメリットなどを解説します。
再雇用制度や嘱託社員の意欲を保つポイントも説明しますので、嘱託制度について詳しく知りたい方は、ぜひ確認してみてください。
※定年退職の現状とこれから|年齢引き上げや継続雇用制度についても解説
※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!
ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
嘱託の定義について
嘱託は、非正規雇用で特定の業務や仕事を依頼し任せることを指します。嘱託社員はそのような業務を依頼された従業員にあたりますが、契約社員や業務委託との違いはあるのでしょうか。嘱託社員の具体例も含めて解説します。
嘱託社員と契約社員の違い
嘱託社員と契約社員の主な違いは労働時間にあります。契約社員の場合にはフルタイム契約するケースが多くなっていますが、嘱託社員の場合には週に5日未満のケースもあります。柔軟に労働時間を設定できる点が嘱託社員の特徴とも言えるでしょう。
雇用形態上では、嘱託社員も有期雇用契約を結んでいる労働者ですので、契約社員の形態の一つと言えます。
多くの場合には、定年を迎え、定年退職後に再雇用された従業員を「嘱託社員」と呼称するケースが多くなっています。高齢でベテランの社員を雇用し、若手の育成指導を行う目的で嘱託制度を設けている企業が多いためでしょう。
契約社員と類似している点がありますが、会社によっては労働条件や待遇などに違いを設けている場合も存在します。
嘱託と業務委託との違い
業務委託と嘱託の違いは雇用関係にあります。業務委託の場合には企業と雇用関係は締結せずに、業務の依頼のみを受けます。しかし、嘱託の場合には雇用関係を締結するケースが多くなっています。
雇用関係を結ぶということは、従業員を雇用保険や社会保険などに加入させなければいけません。また、労災の手続きを進める必要もあるでしょう。
嘱託社員はこうした保険にも加入できる点が特徴としてあります。ただし、会社によっては雇用関係が発生しない嘱託社員制度を設けている場合もあるため、その場合は業務委託と同じような意味となります。
嘱託社員は、企業によってその定義や意味が異なっています。自社内で嘱託制度を設ける場合には、詳細なルールや契約基準を定めておきましょう。
嘱託社員雇用の具体的な事例について
嘱託で労働契約を締結する場合には、どのような事例があるのでしょうか。具体例としては下記のようなケースがあります。
ケース① 定年を迎えた労働者を再雇用する
多くの企業が定年退職の年齢を60歳、もしくは65歳と定めています。しかし、近年では少子化の影響により労働人口が減少しているため、企業では人材不足が深刻化しています。したがって、経験豊富でスキルもある定年を迎えたベテランを再雇用し、労働力不足を補う傾向があるのです。
ケース② 専門的なスキルや技術を持つ人材に業務を依頼する
その他には、医師や弁護士などの専門スキルを保有する人材を嘱託社員として雇用するケースがあります。専門スキルの保有者を正社員雇用する場合、高額な給料や保険料を支払う必要があります。しかし、嘱託契約であれば労働時間も短くできるため、人件費を抑えられるのです。
※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!
ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
なぜ嘱託社員が必要とされているのか
嘱託社員が必要とされている理由には、主に下記のような要因があります。
理由① シニア世代の再雇用で労働力を補てんする
多くの企業では60歳、もしくは65歳を迎えると定年退職となります。しかし、現在では前述のように少子化による労働人口減少のため、企業でも働き手が少なくなっている現状があります。
そこで定年を迎えた労働者を再雇用し、労働力の確保や補てんを行おうとする動きが活発化しているのです。
また、シニア世代社員のノウハウやスキルを若手に伝え、企業の生産性をより高める意図もあることから、嘱託社員の制度は注目されています。
※シニア層の仕事観|定年後も7割以上の方が働きたい
理由② 老後資金の確保のため
現在では年金の受給開始年齢が65歳からとなっているため、60歳で定年を迎えると5年間は収入がない状態になってしまいます。そうなれば、貯金から生活費などを捻出するしかありません。
こうした現状により、シニア世代でも老後の生活資金確保のために働きたいという人も多くなっていることから、嘱託社員制度が導入されるきっかけとなっているのです。
法律でも「高年齢者雇用安定法」として、働く意欲がある高年齢者がいる場合には、65歳までの雇用を義務付ける施策が定められています。したがって、今後も嘱託社員として勤務する労働者は増加していくでしょう。
※定年制度の下限年齢が変更?2025年65歳定年制への対応方法と注意点
嘱託社員の制度を導入するメリット・デメリットについて
続いて嘱託社員のメリットとデメリットも確認しておきましょう。嘱託社員となる従業員と雇用する企業ではメリット・デメリットは異なるため、分けて解説していきます。
企業側が嘱託社員を雇用するメリット・デメリット
<メリット>
① ベテラン社員のノウハウを生産性向上に活かせる
定年を迎えたベテラン社員は、業務に関するスキルやノウハウ・知識などが豊富です。
そのため、定年を迎えても嘱託社員として再雇用し、若手や新人の指導を行ってもらえば、企業全体としての生産性向上に繋がるでしょう。
② 人件費の削減効果がある
嘱託社員を雇用する際は、定年前よりも給与や勤務日数を削減して契約することが大半です。支給する給与が下がれば、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料の会社負担も軽減するでしょう。
したがって、企業にとっては人件費の削減効果を得られます。また、前述のように弁護士や医者などを嘱託社員として雇えば、正社員雇用よりもコストを抑えられる点もメリットです。
<デメリット>
① すぐに辞職されるおそれがある
定年後に嘱託社員として雇用される場合、正社員雇用時に比べ給与などが低下します。
また、役職なども外され、これまでとは違った待遇になることから、モチベーションが下がり、嘱託社員として雇用しても、すぐに辞職してしまう可能性があるため注意が必要です。
② 契約更新の手続きが手間である
嘱託社員を雇用する際は、雇用期間を1年程度にして契約するケースが大半です。そのため、1年ずつの契約期間を更新していく手続きが煩雑になるでしょう。
更新の際に労働条件の交渉も行う場合は、さらに手間が掛かるためデメリットとなります。
従業員が嘱託社員となるメリット・デメリット
<メリット>
① 勤務日数や労働時間を調整できる
正社員の場合には勤務日数や労働時間を減らすことは基本的にできませんが、嘱託社員となれば交渉次第で調整が可能です。
特に定年を過ぎてからの勤務は体力的に苦労するため、少ない日数で働けるのは従業員にとって大きなメリットでしょう。
② 仕事上のプレッシャーから解放される
定年前に責任ある役職に就いていた正社員であれば、嘱託社員となることで仕事上の大きなプレッシャーから解放されるメリットもあります。
また、親しみのある職場や仲間と働ける利点もあるため、転職するよりも苦労なく勤務できるでしょう。
<デメリット>
① 給与が低下してしまう
嘱託社員となる場合は、正社員時に比べて給与が低下してしまいます。賞与も支給されないケースもあるため、定年退職後も収入が多く欲しい方にとっては不満を感じやすくなるでしょう。
また、責任ある仕事は任されないことから、モチベーションが上がらない可能性もあります。
② 継続して勤務できない可能性がある
嘱託社員は派遣社員や契約社員などと同じように、有期雇用であることから契約更新ができない可能性も存在します。
したがって、もし契約が途絶えれば仕事を続けられないデメリットがあります。正社員に比べて、不安定な雇用形態である点は把握しておく必要があるでしょう。
| - | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 企業 | ベテラン社員のノウハウを生産性向上に活かせる 人件費の削減効果がある | すぐに辞職されるおそれがある 契約更新の手続きが手間である |
| 従業員 | 勤務日数や労働時間を調整できる 仕事上のプレッシャーから解放される | 給与が低下してしまう 継続して勤務できない可能性がある |
※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!
ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
定年後再雇用制度の概要
現在では定年を迎えても定年退職後に再雇用してもらうことが可能です。そこで今度は定年後の再雇用制度について詳しく確認しておきましょう。
※定年退職の現状とこれから|年齢引き上げや継続雇用制度についても解説
高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法は、高年齢者が継続的に勤務できる環境を構築するために制定された法律です。1971年に制定され、1986年には名称が変更となり高年齢者雇用安定法と定められました。
その後も改正は続き、2013年には定年を「60歳未満」とすることが禁じられ、さらに下記の雇用確保措置のいずれかを行うことが義務付けられたのです。
① 定年制の廃止
② 定年を65歳までに引き上げる
③ 65歳までの継続雇用(再雇用)制度を導入する
定年後再雇用制度は③の義務から企業が講じている措置であり、定年を迎えた社員は希望すれば再雇用され勤務可能となります。
高年齢雇用継続給付金の概要や種類
再雇用されて勤務する場合、定年前の給料と比較すると30~50%程度低くなるケースが多いとされます。こうした定年後の賃金低下を補てんする目的で定められた制度が、高年齢雇用継続給付金です。
なお、高年齢雇用継続給付金には下記の2種類があります。
① 高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降も企業で継続的に勤務し、給与額が低下した従業員に支払われる給付金です。定年退職後に失業保険を受け取ることなくすぐに再就職した人や、失業保険を受けずに同じ企業で勤務し続けた人が受給できます。
② 高年齢再就職給付金
60歳以降に退職し失業保険を受給しており、再就職時に失業給付の支給日数が残っていて、給与が低下した場合に支給される給付金です。支給要件として基本手当の被保険者期間や支給残日数などがあります。
いずれもハローワークから支給されますので、受給条件等は確認しておきましょう。
再雇用後にも5年ルールは適用されるのか
有期雇用で勤務している従業員がいる場合、雇用期間が5年を超えると会社側は無期雇用の申し入れを受け入れる義務があります。これは改正労働契約法で定められた「5年ルール」もしくは「無期転換ルール」と呼ばれる規定です。
当該規定に従えば、60歳から65歳まで勤務した再雇用者からの申し入れ時にも、無期雇用としなければいけません。しかし、高度専門職や定年後の再雇用の場合、定められた条件を満たせば5年ルールの対象外とすることが可能です。(有期雇用特別措置法による特例です)
なお、当該特例のルールを受けるには、都道府県労働局から事前に認定を受けなければいけません。無期転換の申込権が発生してからでは遅いため、制度の適用を受けたい方は早めに準備しておきましょう。
※中小企業向け採用サービスで求人のプロが代行し、応募効果を最大化!
ワガシャ de DOMOで求人の応募数不足を解決!
⇒ワガシャ de DOMOの資料を見てみたい
嘱託社員のモチベーション維持のためのポイントとは
嘱託社員となると給料の低下や重大な仕事が任されないことから、モチベーションが低下してしまう可能性があります。モチベーションを維持するためのポイントも把握し、嘱託社員にもいきいきと働いてもらえるような体制を構築しましょう。
モチベーション維持のためには下記のようなポイントがあります。
ポイント① スキルを活用できる業務に就いてもらう
これまでに習得した技術や知識を活かせる仕事に就けば、働くモチベーションは維持できるでしょう。定年前とまったく異なる仕事に就いてもらうのではなく、その嘱託社員が以前行っていた業務に関連する仕事を割り振るのが良いかもしれません。
また、嘱託社員は経験やスキルが豊富ですので、若手社員のサポートや指導を担当してもらうと効果的です。その際には、どのような役割をこなして欲しいか、事前に伝えておくと良いでしょう。
ポイント② やる気次第で給料や待遇が向上する環境を用意する
嘱託社員となると、給料は低下し大きな仕事も任されなくなるのが現実です。しかし、働く意欲が強い嘱託社員からすれば、こうした環境はモチベーションを維持できないでしょう。
したがって、嘱託社員にはやる気次第で給料や待遇が向上する環境を用意すると効果的です。仕事内容についても簡単なものだけではなく、本人の体力やモチベーションも勘案して、難しい仕事を任せてみるのも良い方法です。
ポイント③ 若手の人材育成に関わる業務を任せる
最後のポイントは人材育成にも携わってもらう点です。
知識やスキルが豊富な嘱託社員には、OJTなどで現場社員の育成担当になってもらうとモチベーションも向上するでしょう。指導力を高めるため、新たにマネジメントスキルを習得してもらうのも効果的です。
また、若手や現場社員のための研修内容を、経験豊富な嘱託社員に考えてもらうのもおすすめです。育成会議や意見交換の場にも参加してもらい、良いアイディアを出してもらいましょう。
嘱託社員の活躍にはメリット・デメリットを把握した体制構築が重要
嘱託社員の概要や契約社員・業務委託との違い、メリットやデメリット、再雇用制度や給付金制度などを説明しました。労働力が不足している今の日本では、嘱託社員を活用して生産性を向上させる取り組みは不可欠と言えます。
しかし、定年を迎えた方に活躍してもらうためには、注意すべき点やメリット・デメリットも把握しておくことが大切です。ぜひ、本記事を確認しながら、嘱託社員が充実したライフワークを送れるように体制を構築してみてください。

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。
「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。
アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/
求人情報誌発行・人材派遣の会社で広告審査や管理部門の責任者を18年経験。 在職中に社会保険労務士試験に合格し、2005年に社会保険労務士杉本事務所を起業。
その後、2017年に社会保険労務士法人ローム(本社:浜松市)と経営統合し、現在に至る。 静岡県内の中小企業を主な顧客としている。
顧客企業の従業員が安心して働ける環境整備(結果的に定着率の向上)と、社長(人事担当者含む)の悩みに真摯に応えることをモットーに活動している。