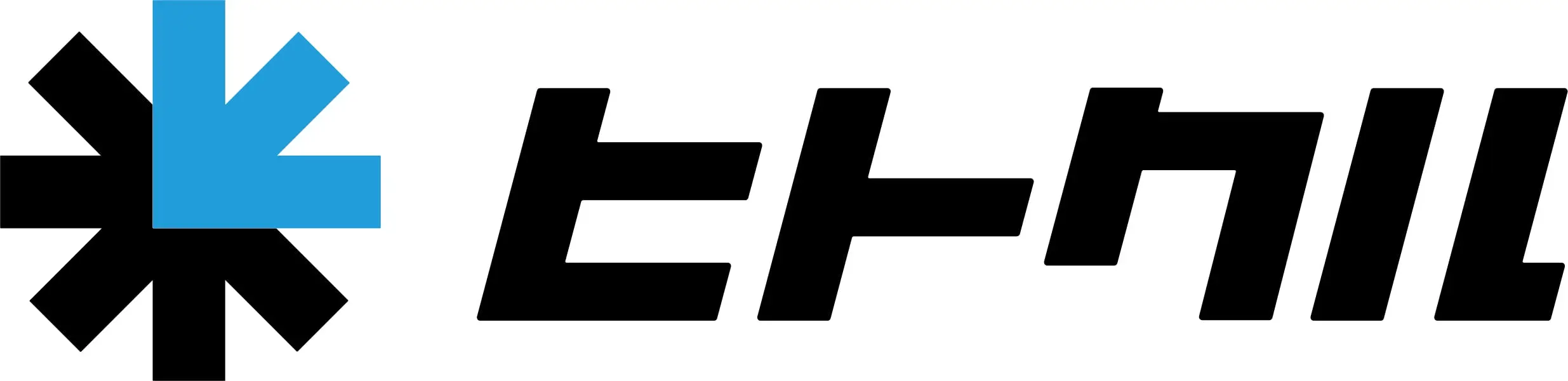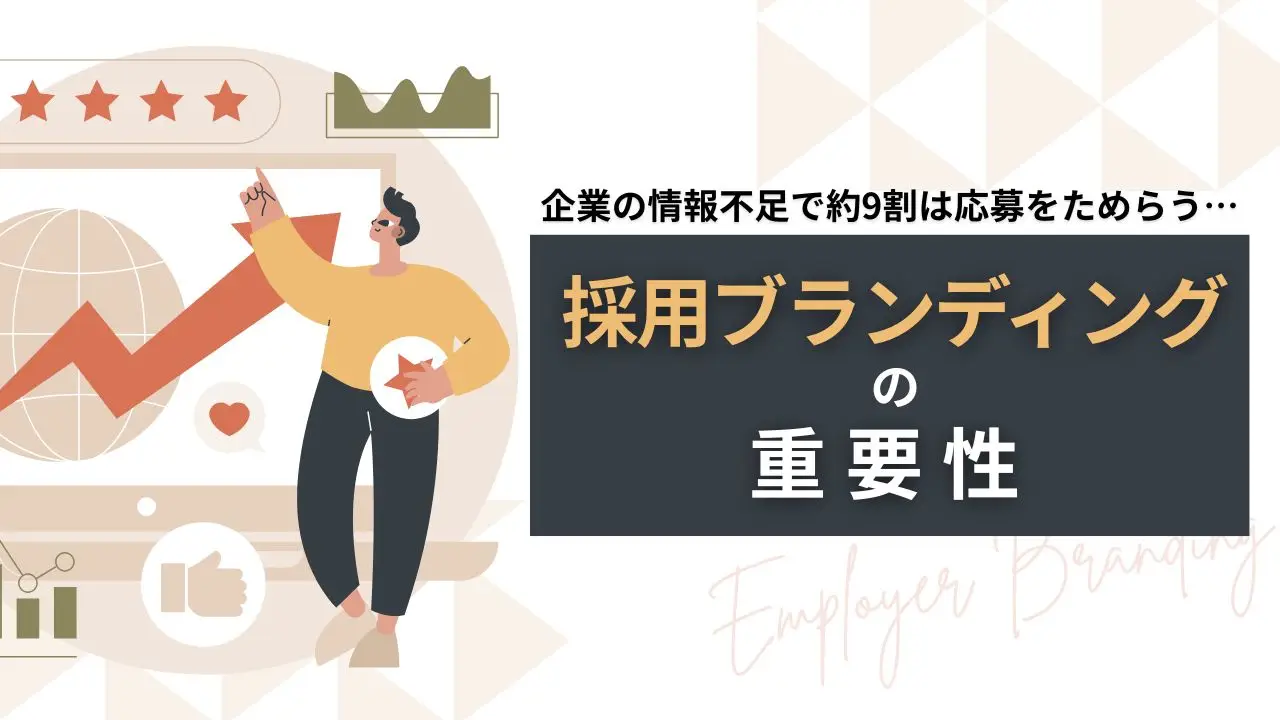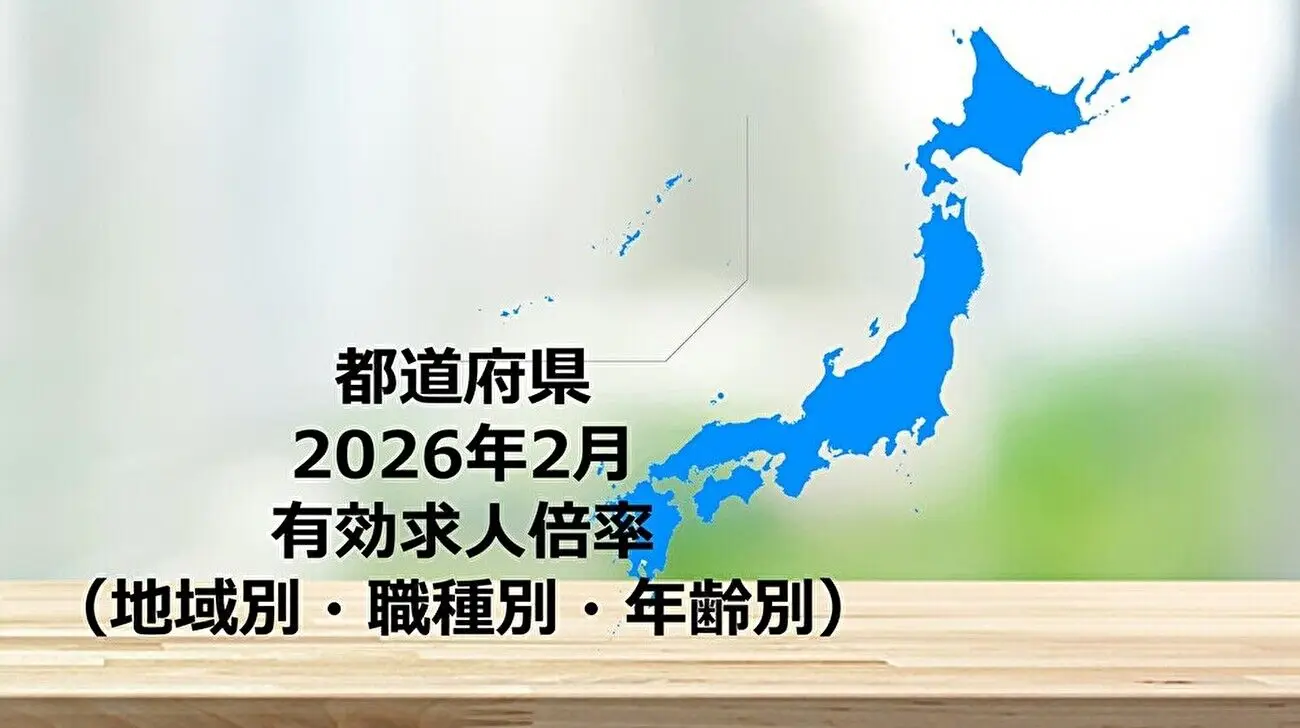
おすすめの新卒採用手法15!選び方や見直し方法も解説
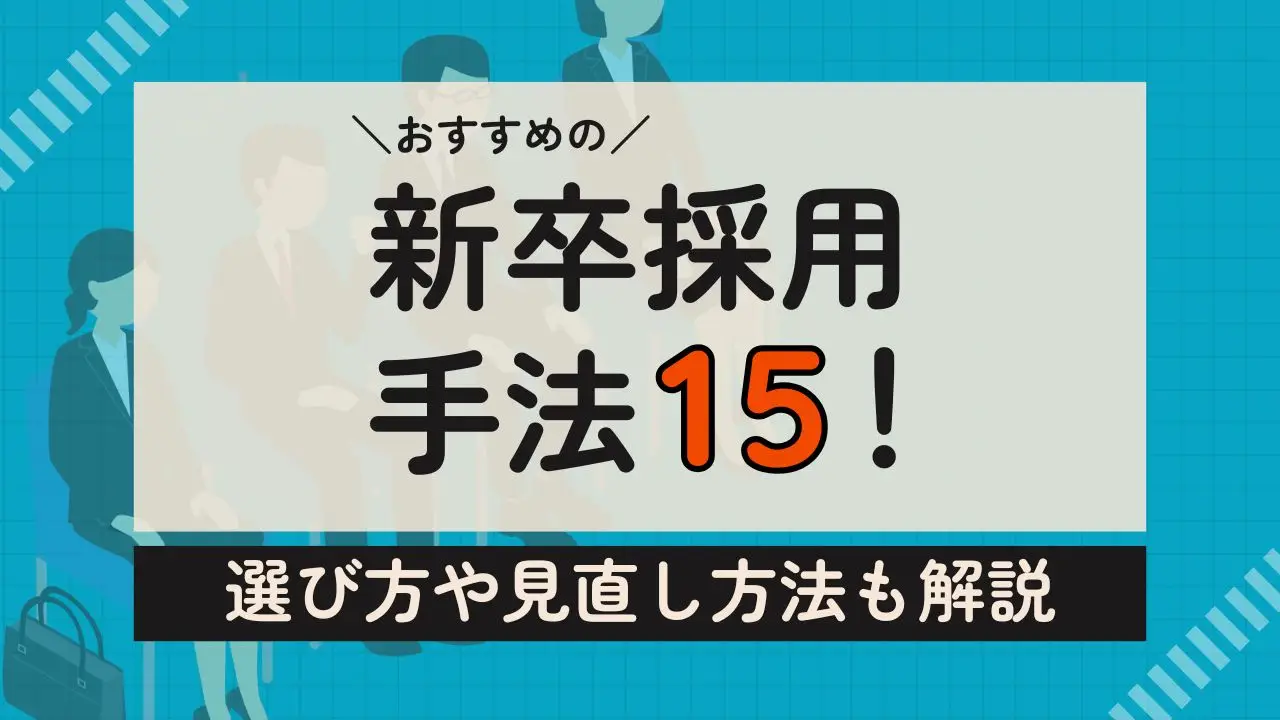
近年の新卒採用では、新卒者向け就職サイト・合同企業説明会といった主流的な手法だけでなく、SNS経由での人材採用やダイレクトリクルーティングなど、多様な採用方法・手法を取り入れる企業が増えてきています。
少子高齢化にともなう人材不足・人材側の働き方の多様化などを背景に、新卒者の確保において複数の手法の採用を検討する企業は少なくありません。
この記事では、新卒採用の目標達成を目指す人事・採用担当者向けに、おすすめの新卒採用手法をご紹介しつつ、それぞれの選び方・見直し方法などについても解説します。
※新卒採用スケジュールを立てる際の基礎知識|近年の流れやポイントも解説
新卒採用とは
そもそも新卒採用とは、学校を卒業する新規学卒者の在学中に採用選考を実施し、内定者につき卒業後すぐ入社させる採用手法のことをいいます。
大卒者の採用など、例年大々的に行われるケースが多いことから、いわゆる「新卒一括採用」と呼ばれることもあります。
実際、大手企業では年間数百人以上を採用することは珍しくなく、企業にとってはフレッシュな若手人材をまとめて採用できるメリットがある一方、採用コストは高くなりがちです。
また、少子化によって人材確保が難しくなる中、新卒者を採用するのが難しいと感じている企業は増加傾向にあります。
※新卒者の通年採用|企業が導入するメリット・デメリットを解説
新卒採用と中途採用の違いとは
新卒採用と対極にあたるのが中途採用で、それぞれ、採用人数や採用にあたっての目的などが異なります。
以下、主な違いをまとめました。
新卒採用 |
|
中途採用 |
|
※最新の中途採用手法のトレンドは?主要な手法14種類を徹底比較
新卒採用手法を選ぶ際の注目点
新卒採用にあたり、具体的な採用手法を選ぶ際は、次にあげる点について十分検討した上で判断することが大切です。
※中小企業が採用に苦戦する理由|人材獲得対策や成功事例も解説
採用要件と一致しているか
採用手法を選ぶ際は、その手法が自社の採用要件にマッチするかどうか、よく考えてから選びましょう。
例えば、求人サイト・就活サイトに自社の情報を掲載する場合、採用要件を満たすユーザーが利用するものと選ばなければ、自社が求める人材と出会うのは難しくなります。
文系と理系のどちらを採用するのか、学歴を重視して採用するのか、特殊な経験や語学力などに注目して採用するのかなど、要件次第で検討すべき採用手法は異なります。
自社の求める人材の採用が難航している場合、採用要件にマッチする採用手法を選べていない可能性を疑ってみましょう。
費用対効果が高いか
採用手法の中には、基本的に無料で利用できるものもあれば、コストが発生するものもあります。
どのような手法を選ぶにせよ、できるだけコストを抑えたいところではありますが、そのために母集団形成がままならないようであれば手法の見直しが必要です。
逆に、高額なコストをかけて採用に成功しても、予算を圧迫するような結果になってしまっては本末転倒です。
よって、採用手法を選ぶ際は、費用対効果が高い手法を意識して選ぶことが大切です。
選ぶポイントとして、どのような人材を、何名採用したいのかを明確にすると、自社のニーズにマッチする採用手法を選びやすいはずです。
※採用コストとは?平均相場と採用単価の削減方法・無料サービスを紹介
十分な成果が出るか
採用要件・費用対効果の面で優秀と判断できても、自社で十分な成果が出そうかどうかは、もう一歩踏み込んで検討が必要です。
例えば、地元で働きたい人材を採用するにあたり、地元密着型の求人サイトやイベントへの参加を試みたとしても、参加スタッフの人数が足りない場合は十分な成果が期待できないかもしれません。
しかし、採用担当者の一人がSNS運用経験のある人材の場合は、SNS採用に舵を切ることで、工数を減らして応募者を増やすことに繋がるかもしれません。
企業が置かれた状況によって、一見良さそうに思える方法にも穴がある可能性があるため、その点にも注意してください。
新卒採用を始める時期
自社で新卒採用を始める時期に関しては、準備も含め、概ね次のようなイメージで捉えるとよいでしょう。
<翌年3月卒業・4月入社の人材採用のケース>
時期 | 活動 |
卒業1~2年前 |
|
卒業前年3月1日 | 一般的には広報活動の解禁日となるため、各種求人媒体等に情報を掲載し、学生からの応募受付を行う |
卒業前年6月1日 | 選考が解禁されるタイミングのため、多くの企業はここから書類選考・面接を本格化する |
なお、こちらはあくまでも一般的なタイミングとなり、経団連に加盟していない企業の場合は、それぞれの基準で時期を決めることもあります。
その他、あえて他社と時期をずらして新卒採用を行い、より多くの学生と出会うチャンスを作っている企業も一定数存在しています。
おすすめの新卒採用手法15選
新卒採用で用いられる手法は数多く存在しており、本記事では近年登場した新しいものも含め、15種類の手法をご紹介します。
就活サイト
就活サイトとは、就職情報サイトの一種で、新卒採用においては一般的な採用手法の一つに数えられます。
学生が企業情報を検索・収集できる仕組みになっており、興味がある企業を見つけたら、学生はサイトを介して「エントリー」を行い、求人に応募します。
就活サイトの利用にあたっては、次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット |
|
|
なお、サイト内で自社の情報を露出させたい場合、上位表示にあたりオプション料金を支払わなければならないため、その点にも注意して利用したいところです。
合同説明会・イベント
採用手法としての合同説明会・イベントには、主に就活サイト等を運営する企業・大学などが主催する学内セミナーなどが該当します。
説明会・イベントに出展し、イベント参加者からの応募を集めるのが、企業の主なミッションとなります。
合同説明会・イベントに出展するメリット・デメリットとしては、次のようなものがあげられます。
メリット | デメリット |
|
|
※転職フェアとは|主要フェアや企業側の出展準備のポイントも解説
人材紹介・リファラル採用
人材紹介やリファラル採用と聞くと、中途採用向けの手法と考える人は多いかもしれませんが、近年では新卒採用においてもこれらの手法が活用されています。
人材紹介に関しては「新卒紹介」と呼ばれることもあり、自社が求める人物像にマッチする人材を紹介してもらった後、面接等により選考・採用を進める流れとなります。
リファラル採用は、自社の社員から友人・知人等を紹介してもらい候補者を募る点で、人材紹介と違いがあります。
メリット | デメリット |
<人材紹介>
<リファラル採用>
| <人材紹介>
<リファラル採用>
|
※今後絶対に抑えておくべきリファラル採用!メリット・デメリット、促進方法と事例を解説
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、自社が求める人材を企業側で探し、直接的にアプローチをかける採用手法です。
採用担当者は、データベースの中から人材のプロフィール等を見てスカウトを行うため、自社にマッチする人材を直接探すことができます。
この採用手法のメリット・デメリットとしては、次のようなものがあげられます。
メリット | デメリット |
|
|
※ダイレクトリクルーティングに注目が集まる理由や導入方法・サービスを比較
インターンシップ
インターンシップは、いわゆる学生の「就業体験」にあたるものです。
学生に職場で仕事を体験してもらい、自社への入社イメージを持ってもらうほか、学生の潜在的なスキルを確認する目的で実施されます。
近年特に注目されている採用手法の一つで、インターンシップで取得した学生情報を採用活動に活用できるようになったことも一因と考えられます。
メリット | デメリット |
|
|
【参考記事】
インターンシップ採用とは?種類や特徴、導入手順について徹底解説
SNS採用
SNS採用とは、自社のSNSアカウント等を通じて、求職者に対してアプローチする採用手法のことを指します。
利用するSNSは企業によって異なりますが、投稿した内容がバズれば、広告費をかけることなく自社について認知してもらえるチャンスがあります。
より本格的に運用するのであれば、専門の代行業者に依頼して投稿するコンテンツの内容を考えてもらったり、広告機能を利用したりする方法も選べます。
メリット | デメリット |
|
|
【参考記事】
SNS採用の活動のポイント|狙える効果やメディア別の活用事例も紹介
オウンドメディア
各種サイト・ブログなど、自社のオウンドメディアを立ち上げ、新卒者を募集する方法が該当します。
就活サイトと異なる点は、基本的に文字数や掲載情報の制限がないことで、自社が新卒者に伝えたいことを好きなように発信できるのが魅力です。
求人・採用に関する情報だけでなく、自社の事業内容やミッション、働いている社員の声など、多様な情報を一つのメディアで発信することができます。
メリット | デメリット |
|
|
※オウンドメディアリクルーティングとは?メリット、注意点、始め方を解説
ハローワーク
新卒採用では意外に感じられるかもしれませんが、ハローワークでは新卒向け求人情報を掲載することも可能です。
こちらの採用手法を利用するケースとしては、例えば本社・拠点が地方にあり、かつその地方向けの求人サイト等がない場合などが考えられます。
都市圏では他の採用手法を選んだ方が有利かもしれませんが、地方においてはまだまだハローワークの有用性が高いところもあるため、臨機応変に使い分けたいところです。
メリット | デメリット |
|
|
※【画像&事例付き】ハローワークでの求人の出し方は?手続きの流れや注意点を解説
大学就職課
いわゆる「キャリアセンター」や「就活支援センター」などが該当し、このような課は各大学に設置されています。
日本中の大学に、同時に自社の情報を掲載できる仕組みはないため、基本的に大学・学部を選んでから情報掲載という流れになります。
学生説明会を行ったり、学生のあっせん・紹介を促してもらったりすることもでき、関係性構築に成功すれば次年度以降の採用活動でもサポートが期待できます。
メリット | デメリット |
|
|
自社ホームページ
オウンドメディアではないものの、自社で会社紹介等を目的としたホームページをすでに持っている場合は、そちらに新卒採用向けの情報を盛り込むのも一手です。
例えば、地元などで自社の認知度がある程度高い場合は、地元人材が求人を見て応募してくれる可能性があります。
SNS採用を行っている場合は、プロフィールに自社ホームページのリンクを貼っておくと、自社に興味を持った人材がホームページに移動する導線を作ることができます。
メリット | デメリット |
|
|
※採用サイトはどんなコンテンツが必要? 作成メリットとポイントを解説!
ミートアップ
ミートアップとは、求職者と社員が気軽な雰囲気の中で交流を行い、その中で「自社にマッチする学生を見つけたら選考に繋げる」という採用手法です。
一般的には、あるテーマをもとにイベントを開催し、参加者とのコミュニケーションを通じて自社を知ってもらうための手法として知られています。
新卒採用向けミートアップでは、企業説明と座談会を兼ねるような形式で開催され、自社に興味を持った人材を選考に案内するケースが多く見られます。
メリット | デメリット |
|
|
※採用ミートアップとは?意味とメリットや注意点・実施方法を解説
逆求人採用
新卒採用における逆求人採用とは、学生側が「逆求人サイト」に自己PRなどの情報を掲載し、それを見て興味を持った企業がアプローチをかける手法のことをいいます。
企業側と学生側の立場が逆になった採用手法ですが、企業としては学生の現在の能力・ポテンシャルについて把握した上で採用できます。
例えば、地方の中小企業など「求人媒体での露出が難しい」企業の採用活動においては、逆求人採用が有利に働くことが予想されます。
メリット | デメリット |
|
|
※逆求人って何? 活用するメリット・デメリットとおすすめサービスを紹介!
Web広告
新卒向けの各種ツールにこだわらず、デジタルマーケティングの手法を応用したWeb広告を用いて、新卒者の応募数を増やす方法もあります。
就職活動にインターネットを活用する機会が増えたこともあり、あえてライバル他社とは異なるルートで広告を配信して、応募者数や応募者の質を改善しようと試みる企業は少なくありません。
適切な運用を実現するにあたり、ノウハウは必要になりますが、差別化を図る上では良い選択肢の一つです。
メリット | デメリット |
|
|
※理想的な求人広告とは?|種類や料金、おすすめの求人媒体についてご紹介!
採用代行
採用代行は、自社で行う採用活動の一部、または全部の代行を行うサービスのことです。
自社に専任の新卒担当者がいない場合や、重要度が比較的低めの業務を任せたい場合などに利用されるケースが多く見られます。
採用のプロが業務を代行するため、安心して作業を依頼できるのもポイントです。
メリット | デメリット |
|
|
なお、選考や面接といった、採用活動の“コア”にあたる業務に関しては、原則として自社で対応するようにしましょう。
※採用代行サービス(RPO)は何ができる? 業者の選び方や注意点を解説
人工知能マッチング
近年注目を集めている新しい採用手法として、人工知能(AI)マッチングがあげられます。
プロフィール・エントリーシート添削・自己分析履歴などをAIが分析し、それぞれの学生に合った企業とマッチングを図るというツールです。
ツールによっては学生のLINEを介して連絡できるものもあり、そのようなサービスでは開封率も高い傾向が見られます。
メリット | デメリット |
|
|
新卒採用の流れ
新卒採用をスムーズに進めるにあたっては、概ね次のような流れを意識して、準備や選考・対応を行いましょう。
計画・スケジュールを立てる
新卒採用に臨む際は、まず採用計画を立て、それをもとに採用スケジュールを立てていきます。
採用計画に関しては、必ず次の2点を具体化させましょう。
必要な採用人数 |
|
自社が欲しい人材像 | 経営理念、ビジョン、高い成果を出す人材に共通する行動特性(コンピテンシー)などをもとに、自社が欲しい人材像を明確化する |
上記内容がまとまったら、採用活動を本格化するタイミング、説明会・インターンシップ等の開催時期につき、入社後の研修予定も込みでスケジュールを立てます。
※新卒採用スケジュールを立てる際の基礎知識|近年の流れやポイントも解説
※採用計画の効果的な立て方とは?手順と準備のポイントを解説!
採用基準・手法を考える
採用計画で定めた「自社が欲しい人物像」は、最終的に採用基準にまで落とし込む必要があります。
具体的には、実際に存在している人物を具体的に設定する「ペルソナ設定」を行い、例えば次のような情報を設定していきます。
- 基本情報(性別や住んでいる地域など)
- 最終学歴
- 性格、価値観
- 家族構成および人間関係
- ライフスタイルに関すること(趣味など)
一通り考え終わったら、そのペルソナに対して「自社でどのように活躍して欲しいのか」を具体化する作業に進みましょう。
同時に、そのようなペルソナはどんな企業に応募する可能性が高いか、自社に魅力を感じるとしたらどのような点かについても考察し、その上で適切なアプローチが可能な採用手法を選択します。
※採用基準の決め方|具体的な設定方法や重視すべきポイントなどを解説
採用に必要な準備をする
採用手法を選んだら、いよいよ採用活動を本格的に進める段階に入りますが、まずは事前準備の時間を確保することが重要です。
例えば、企業合同説明会に参加するのであれば、プレゼン内容や資料の中身をしっかり作り込まなければなりませんし、会場設営や当日の対応についても、参加スタッフで事前に情報共有する必要があるでしょう。
また、選考後に面接に進む状況を想定して、応募者に良い印象を与えられるような会場選び、面接官の設定や役割分担、面接評価シートや質問内容の決定についても進めていきます。
面接官に時間をとってもらい、事前にロールプレイングを実施するのも忘れないようにしたいところです。
選考を進める
新卒者の選考においては、基本的に人材の将来のポテンシャルを中心に評価することになります。
それを踏まえた上で、準備段階から応募、書類選考、筆記試験、適性検査、面接といった一連の流れである「採用フロー」を考えておき、選考を進めていきます。
どのような採用フローを設けるのかについては、企業によって正解が異なるため、過去の例を踏襲するだけではなく、次のような視点からフローを考えることをおすすめします。
- 採用フロー上で自社の魅力を人材側に伝えるにはどうすればよいか
- 優秀な人材へのアプローチをどうすべきか
例えば、人材のマッチ度を確認する上では、複数回面接を行うのが望ましいとされます。
しかし、能力が高い人材は一気に社長面接に進むようなフローを考えておくと、人材側の心をつかむことに繋がるでしょう。
内定者への対応を行う
選考の結果、無事内定者が決まったら、内定通知の出し方、内定後の業務フローを決定して対応を進めていきます。
自社が内定を出した人材の多くは、おそらく他の企業からも内定をもらっていることが予想されるため、迅速かつ丁寧な対応を心がけたいところです。
特に、面接後から時間が空いてしまうと、それだけ他社に流れるリスクが高まるため、内定者とこまめにコミュニケーションを取れるよう工夫しましょう。
内定を出した後も内定者を放置せず、内定者懇親会を開いたり、内定者研修や社内イベントへの参加を促したりと、何らかのフォロー体制を整えておくことをおすすめします。
※内定者フォローとは?効果的なフォローの手順や取り組み事例、便利なツールも紹介!
採用手法を見直す方法
現在の採用手法について、見直しをかける際の主な方向性としては、大きく分けて次の3パターンが考えられます。
採用ステップや時期を見直す
これまで自社で長年実施している採用ステップ、およびその時期に関しては、見直しをかけることで採用活動の効率化が見込める場合があります。
新卒採用において、ある程度一般的なスケジュール感や対応方法は存在していますが、それらは絶対的なものではありません。
採用に割ける人員が少ない中で既存の採用ステップを継続していると、学生が各ステップの結果発表を待っている間に他の企業の内定を承諾したり、選考を辞退したりするリスクが高まります。
面接で好感触を掴んでいた学生を採用できない状況が続いている場合は、現在まで続けてきた採用ステップを一つひとつ見直して、より早く・効率的に選考が終わるよう再検討することをおすすめします。
採用手法を見直す
想定よりもエントリー数が思わしくなく、その点について自社が課題を抱えている場合は、いったん採用手法を見直してみるのもよいでしょう。
近年における学生の就職活動は多様化しており、就活サイトを使わずに働く場所を探している人材も少なくありません。
そこで、エントリー数ではなく「自社のターゲット人材」がどのくらい集まっているのかをチェックできる採用手法に切り替えると、より採用数を増やすことに繋がります。
例えば、採用希望人数が比較的少数であれば、不特定多数への求人公開ではなく、あえて採用したい人材にだけアプローチするダイレクトリクルーティング・人材紹介を選んだ方が、希望の人材を射止めやすいはずです。
効率化を図る
新卒採用のプロセスは複雑なため、専任の担当者がいない企業では、工数の面で対応が限られてしまう部分は否めません。
このような場合は、あえて人の手を借りることで、採用活動の効率化を図ることが重要です。
自社以外から人手を募り、採用活動をサポートしてもらう場合は、採用代行の利用が効果的でしょう。
選考プロセスではなく、応募者増の面でサポートが必要な場合は、求人記事作成や求人広告運用のプロから力を借りる方法もあります。
バックオフィスの規模によっては、経理など他の業務を一時的にアウトソーシングするという選択肢も考えられます。
自社の事情を勘案した上で、必要に応じて最適なサポートを受けましょう。
第2新卒の採用なら「ワガシャ de DOMO」
新卒採用において採用手法を選ぶ際は、それぞれのメリット・デメリットを比較検討した上で、自社にマッチするものを選ぶことが大切です。
昨年以前で十分な成果が出ていないと感じたら、自社が採用したい人材像や、新卒採用で確保したい人員の数なども考慮して、採用手法や採用ステップなどを見直してみましょう。
一方で、少子高齢化により新卒採用は厳しさを増しており、第2新卒や中途採用で補充するケースも増えています。
応募者増を実現したい企業担当者さまは、応募者アップに特化した中小企業向け採用支援サービス「ワガシャ de DOMO」がおすすめです。
採用のプロが豊富なノウハウを活かして求人記事を作成・運用し、業界トップクラスの求人サイトとも連携しながら、様々な求職者にアプローチします。

「ヒトクル」は、株式会社アルバイトタイムスが運営する採用担当者のためのお役立ちサイトです。
「良いヒトがくる」をテーマに、人材採用にかかわる方々のヒントになる情報をお届けするメディアです。「採用ノウハウ」「教育・定着」「法務・経営」に関する記事を日々発信しております。各種お役立ち資料を無料でダウンロ―ドできます。
アルバイトタイムス:https://www.atimes.co.jp/